ここから本文です。
特許制度の制定に貢献した先人たち
福沢諭吉(1835~1901)
略歴

1835年(天保5年)大阪堂島の中津藩士福沢百助の子として生誕。緒方洪庵の適塾で学び、現在の慶應義塾大学の前身となる蘭学塾を創設。「西洋事情」を著し、西洋文化の紹介に務めた。その他の著書に「学問のすすめ」、「文明論之概略」がある。
工業所有権制度に関するエピソード
福沢諭吉は1862年(文久2年)に遣欧使節に翻訳方として加わり、渡欧。そのときに目にした最新技術に驚いた諭吉は特許制度の存在を知り、その普及の必要性に目覚めたといいます。
福沢諭吉が渡欧した当時の西欧諸国では、発明をすれば特許が与えられ、一定期間保護されるため、それによって大きな利益を得ることができました。そのため人々はこぞって新たな技術の開発・改良に取り組み、ひいては、それが国そのものの発展へとつながっていくという産業技術の発展の基礎には特許制度の存在が大きかったのです。
そのことに気付いた諭吉は、著書である『西洋事情』で西洋文化を紹介するとともに特許について以下のように説明しています。
「世に新発明のことあらば、これよりて人間の洪益をなすことを挙げて言うべからず。ゆえに有益の物を発見したる者へは、官府より国法をもって若干の時限を定め、その間は発明によりて得るところの利潤を独りその発明者に付与し、もって人心を鼓舞する一助となせり。これを発明の免許(パテント)と名づく」新しい発明は、国民に利益をもたらします。発明者の権利を認める法律を定め、一定期間、利潤を得られるようにすることで人々はもっと発明をしようとするでしょう。それが日本の発展につながると福沢諭吉は説明しています。
1866年(慶應2年)に刊行した「西洋事情」は西洋諸国の制度や文化などを一般の人にもわかりやすい言葉で書かれていたため、日本中で広く読まれ、諭吉の紹介に共鳴した人は多く、日本でも特許制度を導入しようという声が高まりました。
神田孝平(1830~1898)
略歴
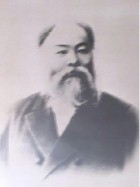
神田孝平は、漢学、蘭学を素養とし、政治・経済・法律・数理・文学・人類学・天文学に通じた人物。
1871年(明治4年)、兵庫県令に任命され、1874年(明治7年)には全国に先駆けて兵庫県会を開いたほか、県庁機構の整備・近代化、梅毒病院・神戸病院附属医学所の開設、馬鈴薯栽培の導入等で、名県令とうたわれた。
工業所有権制度に関するエピソード
神田孝平は福沢諭吉の友人でもあり、福沢諭吉と同様に神田孝平も『西洋雑誌』の中で外国の特許制度を紹介し、日本における特許制度の重要性を説きました。
神田は、発明を「先ず諸新奇の事を分つて三大類となし、第一は万国未曾有の事を発明せし者、第二は他国にて発明せし事を始て自国に学び伝えしもの、第三は古来有来の事に改正を加え足るものなり」と3つに分類し、特に第2番目に挙げた、西欧から新たな技術を導入した場合の利益をどう守るのか。それは、海外との交易を始めたばかりの日本にとって、国内の利益を守るだけでなく、外国との貿易の中で国益を守るためにも、法制度の整備は不可欠だと説いています。
また、神田は、下田で写真術を伝習するのに大金をだした下岡蓮杖が競争者の出現により元手を回収できなかったことを「西洋雑誌」に投稿し、もし特許制度があれば伝習者が保護され、国家富強の源になることを提言しています。そして1871年(明治4年)の日本初の特許法である専売略規則の制定についても西洋雑誌で紹介した制度の内容と似かよっていることなどから、神田孝平はかなりの影響力をもっていたともいわれています。
前田正名(1850~1921)
略歴

前田正名は、農商務省の官僚として、また在野で産業運動を展開した人物。薩摩藩の出身でフランス留学が長く、帰国後、大蔵省・農商務省に入り、1884年(明治17年)に「興業意見」を作成して、健全な産業育成のためのさまざまな提案を行った。
工業所有権制度に関するエピソード
日本初の特許法である専売略規則が1871年(明治4年)に布告されましたが、残念なことにうまく機能せず、わずか1年で執行停止になってしまいました。一方で当時、偽ブランドや模造品が数多く出回り、製品の品質や技術の管理が成り立たなくなりつつあり、市場は大きく混乱していました。商工業のモラルの低下を招くばかりでなく、粗悪品や模造品による品質低下によって、織物、漆器、陶器といった重要輸出品に悪影響を及ぼしました。この状況を打破するには、一度は頓挫してしまった特許制度を整備して粗悪品を取り締まる必要がある。そう考えたのが、当時の農商務大書記官兼大蔵大書記官の前田正名でした。
専売略規則が執行停止した1872年(明治5年)からすでに、全国各地から専売特許制度制定の建白書が何件も出され、特許制度を求める世論が次第に高まってもいました。そういった多くの声の後押しもあって、特許制度再開の準備が始められることになりました。
1883年(明治16年)、前田正名は森有礼の紹介で、農商務省公務局調査課の高橋是清と知り合うことになります。この出会いが、日本の本格的な特許制度整備の大きなターニングポイントとなったのです。その後も二人は、日本の産業の発展について頻繁に意見交換を行っていく事になりますが、このときの意見交換が高橋是清にとって工業所有権制度の「根本」というものについて考えさせられるきっかけとなり、後に専売特許条例の制定作業に従事したといわれています。
岩倉具視(1825~1883)
略歴

1825年(文政8年)公家の堀河康親の次男として生誕。14歳の時、岩倉家の養子となり、1854年(安政元年)、孝明天皇の侍従となる。
明治政府では、参与、議定などの要職を歴任し、右大臣になると、欧米諸国との条約改正を交渉する特命全権大使として、使節団を率いて渡航。その後、自由民権運動を抑え、皇室を擁護する華族制度の確立に尽力する。
工業所有権制度に関するエピソード
江戸幕府が欧米諸国と締結した修好通商条約は関税自主権がないことや治外法権など不平等条約であったために明治政府は長く苦しめられることになりましたが、これらの不平等条約は、1872年(明治5年)に条約改定の協議期限が訪れる事になっていました。そこで、条約改定交渉のための使節団が派遣されました。この使節団は、岩倉具視特命全権大使を筆頭に副使には大久保利通と木戸孝允がおり、総勢103名。1871年(明治4年)11月に横浜からアメリカのサンフランシスコに向かいました。ところが、委任状の不備が判明。条約改正交渉ではなく、欧米の調査に目的を切り替え、2年弱の視察を行う事になります。
使節団は、アメリカの特許局訪問をはじめとして、欧米の特許事情を目の当たりにするとともに、各国の特許関係の資料を大量に持ち帰りました。その際の記録によると、現在の特許局である「パテント、オヒス(Patent Office)」は褒功院と訳されていたようです。不平等条約に関する交渉ではまったく成果が出せなかった使節団ですが、日本での専売特許条例制定作業には大きな影響を及ぼす事となります。
当時の日本は、不平等条約の中の『関税率を協定とする』という項目によって関税自主権もない状況であり、輸入品に関する関税を「原則五分」という低さに抑えられていました。また、治外法権によって、外国人が罪を犯しても取り締まることさえできませんでした。そのため、先進国間との国際競争では圧倒的に不利だったのです。日本の近代化には不平等条約改正が不可欠だと考えられていました。そのため、その後もさまざまな手段がとられることになります。特許関連の法整備も、取引材料の一つとなっていくのです。
井上馨(1835~1915)
略歴

萩藩地侍・井上五郎の次男として生誕。
1864年(元治元年)、禁門の変や第一次長州征伐などでは講和のために尽力し、第二次長州征伐では、芸州口の参謀として活躍し、勝海舟と休戦協定を話し合う。
明治維新後、外務大臣、農商務大臣、内務大臣、大蔵大臣等を歴任し、退任後は元老として活躍。
工業所有権制度に関するエピソード
1885年(明治18年)に専売特許条例が公布され、特許制度が導入されましたが、最初は日本人のみが対象の制度でした。
そのため外国製品の偽造に対する取締りは、特に法律上の根拠がなく、政府は、単に不都合だという理由で取り締まっていたのですが、後には検査を受けていないという事による購入者保護の面が強調される事になります。
しかし、それでは問題が残るため、井上馨外相は、高橋是清に対して外国人にも特許認めるように求めることになります。井上は、外国人にも特許を認めないと模倣を怖れて輸出品がこなくなると指摘しました。それに対して高橋は、不平等条約改正のための切り札として、特許を使ってはどうかと進言したと言います。外国人にとっても、日本で特許を得ることは非常に有用であると考えられていたためです。
いずれにせよ、不平等条約解消と外国人も含めた特許関連の権利保護は、日本の産業発展には欠かせないものという認識は、当時から強くあったのでした。
[更新日 2001年4月23日]