ここから本文です。
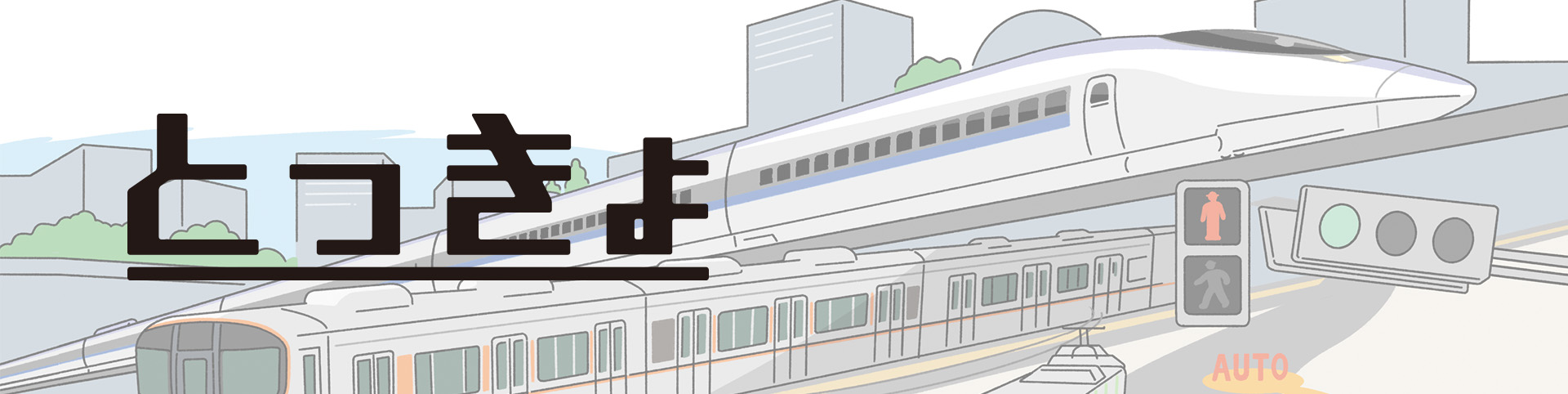
Vol.52
広報誌「とっきょ」2022年3月10日発行
STAFF CLOSE-UP
特許庁の匠
知財にまつわるさまざまな仕事に携わる特許庁のプロフェッショナルにフォーカス。今回は、意匠制度をより使いやすくするための法改正を推進した意匠審査官の匠が登場します。

特許庁総務部国際政策課/
国際協力課課長補佐(意匠政策係長)
平田 哲也
滋賀県出身。2010年入庁。14年審査官。意匠審査に従事し、その後、企画調査課、意匠課にて調査研究や制度普及などを担当。19年よりスウィンバーン工科大学客員研究員として豪州に滞在。20年より意匠課にて令和3年特許法等一部改正を担当。21年10月より現職。
時代のニーズに合わせて意匠法をアップデート
絵を描いたり物を作ったりすることが好きで、学生時代には建築を専攻。中央省庁の説明会に参加し、国家公務員で唯一、デザインを専門とする職種がある特許庁と出会いました。
私たちは意匠制度を通じて、企業をはじめとするユーザーの皆さまのデザイン、ビジネス、イノベーションを支えています。また、意匠制度は、時代とともにアップデートすることが必要不可欠です。昨今、画像、建築物、内装デザインの経営資源としての価値が高まっています。そこで、令和元年意匠法改正により、これらを新たに保護対象とすることを実現しました。私は、衆参両議院における委員会質疑での、答弁書の原案の取りまとめを担当。多数の質疑から、抜本的な改正を目指す意匠法への関心の高さを実感しました。令和元年意匠法改正に関する情報は、特設サイトで一元的に提供。今年の月には、意匠登録事例を特許庁ホームページ上で公開しました。
新型コロナウイルスの感染拡大に対応した手続のデジタル化などの文脈で、令和年にも意匠法を改正。意匠の国際出願の利便性向上のために、条文の草案作成から国会対応まで一貫して関わりました。これからも、私たちは時代のニーズに合った意匠制度を描いていきます。
そして、現在私が担当するのは、意匠分野の国際協力。日本企業が海外でも安定して意匠権を取得し、活用できる環境を実現することが目標です。
「事例から学ぶ 意匠制度活用ガイド」
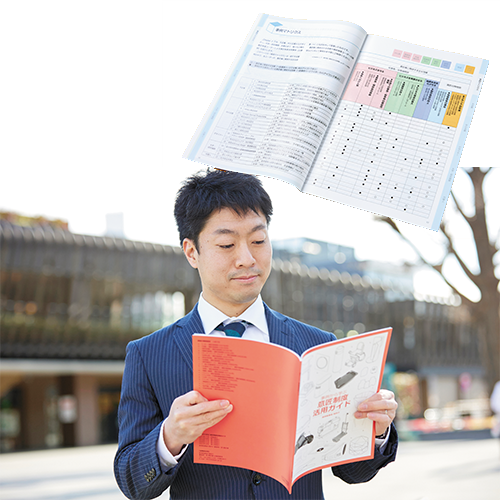
意匠制度の活用方法は模倣品対策にとどまらない。中小企業やデザイナー、大学・研究機関の皆さまにも意匠のことを知ってほしい。そんな思いを込めて作成しました。2021年には「意匠制度の基本」を最新情報に更新。ユーザーへのインタビューを基に、意匠権に期待される効果を抽出した「事例マトリクス」もぜひ参考にしてください。
もっとクローズアップ!
建築物の意匠として意匠登録された上野駅公園口駅舎

東日本旅客鉄道株式会社( J R 東日本)の上野駅公園口駅舎は、改正意匠法により初めて意匠登録された、建築物の意匠の一つ。登録をお知らせするニュースリリースの日は、法律の施行日に続く第二の船出であり、感慨深かったことを覚えています。
休日は子どもたちと絵を描いて過ごしています

7歳と3歳の子どもと遊んでリフレッシュするのが休日の過ごし方。特に、鉄道が大好きな子どもたちのリクエストで、一緒に電車の絵を描いたり、段ボール電車を工作したりしています。