ここから本文です。
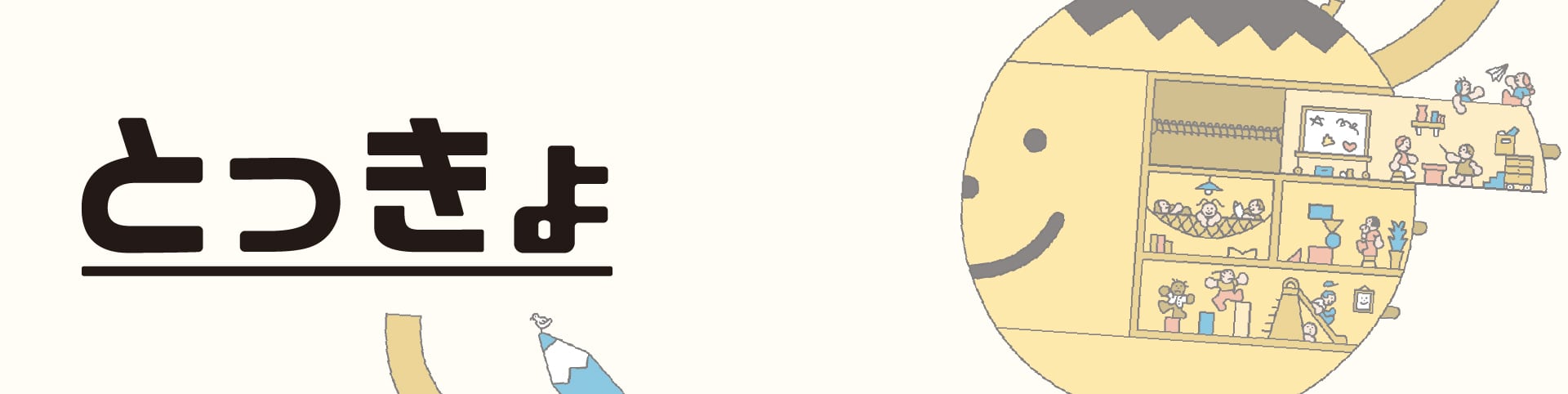
Vol.61
広報誌「とっきょ」2024年7月30日発行
注目のあの話題を徹底解説!
知財TOPICS
特許や意匠、商標など知財にまつわる注目の最新ニュースを、専門家が分かりやすく解説! 今回は、「近大マグロにおける知財活用」と、近畿大学のブランディング戦略との関係について掘り下げます。
TOPIC
「近大マグロ」のさらなる認知拡大を目指し、近畿大学と大学発ベンチャー企業が販売開始
近大マグロの缶詰をモチーフにした文具系新商品が登場

近畿大学と、近畿大学発ベンチャー企業の株式会社アーマリン近大は、登録商標でもある「近大マグロ」の缶詰をモチーフにした文具缶「近大マグロ缶」を、2024年5月16日に販売開始した。本物の缶詰のようなデザインの缶の中には近大マグロ型のゼムクリップとメモ帳が入っており、缶も小物入れとしてリユースできる。また、缶には近大マグロの完全養殖についての情報が記載されていて、面白さの追求だけでなく、近大マグロについての理解を深めるきっかけとなることを目指す。
養殖魚専門料理店「近畿大学水産研究所」の各店舗や近畿大学施設内、オンラインショップで販売。学内イベントなどでのノベルティとしても活用する。多くの全国紙・地方紙・業界紙で紹介され、販売開始から1カ月で約7000個の出荷実績を記録するなど、想定以上の好反応を見せている。
近畿大学水産研究所は、1970年からクロマグロの完全養殖に向けて研究を始め、2002年に世界で初めての完全養殖に成功した。その後は研究を続けつつ、直営の養殖魚専門料理店など事業化も積極的に推進。知財関連では、養殖装置・配合飼料・水温制御システムなどの特許取得(第4005993号ほか)だけでなく、2006年には「近大マグロ」の文字を含む商標を登録し(第4933272号)、製品化やライセンスなど活用の幅が広がった。また、「近大マグロ」は、近畿大学水産研究所で生産、または同様の方法でトータルに生育過程を管理されたマグロしか名乗ることができないので、品質保証の面でも機能している。
「近大マグロ」にまつわる知財が大学のPRに果たす役割は?
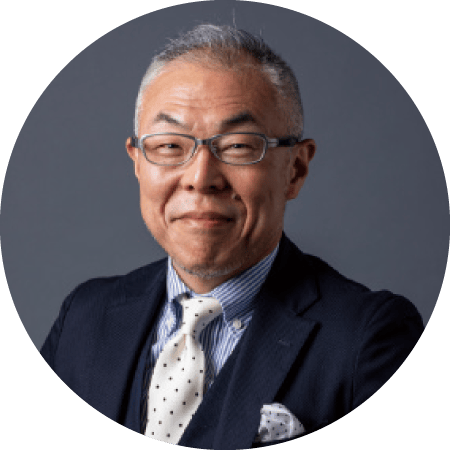
解説
学校法人近畿大学 経営戦略本部長
世耕 石弘氏
奈良県出身。1992年近畿日本鉄道株式会社に入社し、ホテル事業、海外派遣、広報業務を担当。2007年から近畿大学で入試広報課長、入学センター事務長、広報部長、総務部長を歴任し、2020年4月より広報室を管掌する経営戦略本部長を務める。
「近大マグロ」は、建学の精神「実学教育」を象徴するキラーコンテンツ
私たち近畿大学の建学の精神として、古いアカデミズムとは一線を画す「実学教育」というものがあります。研究を続ける資金は自分たちで稼ぐといった自助独立の気風が特色で、世界初のクロマグロの完全養殖も、国からの研究費に頼らず、先に成功したマダイやシマアジの完全養殖の収益を土台に実現させたものです。そうした歴史があるので、近大にとって「近大マグロ」とは、ユニークな研究成果というだけでなく、自分たちの根幹にある建学の精神のシンボルです。
近大の立地する東大阪は、中小企業や町工場がひしめく、下町情緒の豊かな街。近大のブランディングも、庶民的な雰囲気や親しみやすさを重視しています。絶滅の危機にひんしているマグロを救うという意義だけでなく、市民がおいしいマグロを安く食べられるための技術を確立したという点に、近大らしさがあると思います。
実は、私が近大の広報業務に携わるようになった2007年の時点では、完全養殖の成功から4年以上が経過した近大マグロは、学内では旬を過ぎたニュースと見なされ、学校案内などにあまり使われなくなっていました。しかし大学の広報・コミュニケーション戦略のターゲット層である受験生は毎年大幅に入れ替わりますから、常に新鮮でユニークなトピックとして感じてもらえるはずだと考えて、再度フィーチャーする方向に舵を切ったのです。研究であれスポーツであれ、「○○大学といえば●●」という分かりやすいアイコンを掲げられる大学ばかりではない中で、近大マグロのようなキラーコンテンツを持つことができたのは非常に恵まれていたと思います。
学内には、産学連携の窓口として2000年に設置された「近畿大学リエゾンセンター」という機関があります。企業や他の大学との共同研究をコーディネートし、その成果として生まれる特許や商標などの知的財産の管理も一括して行います。近大の産学連携の特色の一つに、大企業ばかりでなく、地元の中小企業からの相談にも積極的に対応していることがあります。その結果、受託研究の件数は現在7年連続で全国1位となっており、技術相談も年間約300件のペースで推移しています。中小企業は判断のスピード感で勝り、商品化につながるケースも多く、これらの事例は学校としての研究成果だけでなく、学生の就職活動の格好のツールなどにもなります。こうした点にも「実学教育」の理念が反映されていると考えています。