ホーム> お知らせ> 国際的な取組> セミナー・シンポジウム> 日欧知的財産司法シンポジウム2016
ここから本文です。
日欧知的財産司法シンポジウム2016
-エンフォースメント戦略の道しるべ~侵害と有効性の判断を考える-
2016年11月18日
- 目次
- → 1. シンポジウム概要
- → 2. ごあいさつ
- → 3. プログラム
- → 4. 講演者情報
- → 5. 参考資料
1. シンポジウム概要
| 日時: | 2016年11月18日(金曜日)10時00分~18時00分 |
| 会場: | ホテルオークラ東京別館地下2階アスコットホール 東京都港区虎ノ門2-10-4 |
| 主催: | 特許庁、独日法律家協会、日本弁護士連合会、弁護士知財ネット、日本弁理士会、日本知的財産協会、日本国際知的財産保護協会 |
| 後援: | 法務省 |
2. ごあいさつ
特許庁長官 小宮 義則
この度、日本国特許庁の主催により「日欧知的財産司法シンポジウム」が開催されます。「日欧知的財産司法シンポジウム」は、独日法律家協会により2年に1回、日独交互に開催しているシンポジウムの流れを汲むもので、本年は対象地域を日欧に広げ、我が国で開催することとなりました。
近年、我が国のみならず、欧米も含め、企業活動のグローバル化が急速に進んでおり、世界各国・地域において、技術・デザイン・ブランドを知的財産として保護できる環境を整備することの重要性が高まっております。日本国特許庁としては、世界最高の知財システムの構築を目指し、特許審査ハイウェイ、特許審査結果の国際発信・利用促進、国際的な知財制度・運用調和に向けた協力等、グローバルな権利の取得・活用を支援する取組を進めて参りました。
このような中で、知的財産権を巡る紛争処理につきましても、グローバルな視点での取組がますます重要になっております。日本国特許庁は、これまでも、行政の立場から、各国の審判官と様々な交流を通じた相互理解の向上等に努めて参りました。今回のシンポジウムでは、独日法律家協会をはじめ、日欧の法曹関係者及び実務家をお招きし、知財に関わる紛争処理に関して議論を深めて頂くこととしました。
シンポジウムのプログラムは、日欧の裁判所及び特許庁による基調講演、欧州の実務家が実演する統一特許裁判所に関する模擬裁判、日欧の実務家による特許侵害訴訟や特許権の有効性に関するパネルディスカッションというバラエティに富んだ内容となっており、参加者の皆様にとって非常に興味深いものになると確信しております。
共催者一同、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

特許庁長官
小宮 義則
独日法律家協会会長 ヤン・グロテア博士
本シンポジウムの開催にあたり、独日法律家協会を代表してご挨拶をさせていただけることを光栄に感じております。
経済がグローバル化し、日本とドイツの関係が緊密なものになる中、法律や経済のあらゆる分野に関して情報や意見を交換することは有用であると同時に実用的であると言えます。そして皆さまご承知のとおり、知的財産に関連する法律はそのなかでも最も重要なものの一つです。このことから独日法律家協会は早くも2009年に、バイエルン州の州都であり、かつ、ドイツ特許法の中心地でもあるミュンヘンにて第1回目の特許法シンポジウムを開催いたしました。2012年には東京で開催された知的財産に関するシンポジウムの支援団体の一つを務めさせていただき、2014年にはミュンヘンにて第3回目となるシンポジウムを開催いたしました。11月18日には欧州及び日本での特許訴訟をテーマに第4回目となるシンポジウムを開催致しますが、この素晴らしい企画は、今後も末永く続いて欲しいと思っております。
近年、特許法はドイツ国内で大きな注目を集めています。6月23日に内閣及び議会において、2013年2月19日に調印された統一特許裁判所に関する協定(UPC協定)が審議されました。協定では統一特許裁判所が原則として全てのEU加盟国を対象とすること、第一審裁判所がそれら加盟国に置かれること、そして控訴裁判所はルクセンブルクに置かれることが決まっています。統一特許裁判所はすでに登録されている欧州内の特許のほか、今後申請される統一特許に関して判決を下します。特許の主要国であるドイツ国内にはデュッセルドルフ、ハンブルグ、マンハイム、ミュンヘンの4つの都市に地方部が置かれるほか、中央部の支部がミュンヘンに置かれることが決まっています。同じく6月23日、残念ながら英国がEUからの離脱を選択したことから、この統一特許裁判所の設置にはもうしばらくの時間が必要となるかもしれません。
独日法律家協会について少しだけお話をさせてください。
当協会は1988年にハンブルグで設立され、現在はおよそ700名が加盟しています。そのほとんどがドイツと日本の法律家ですが、他にも様々な国の方が加盟しており、アメリカやオーストラリアを中心に、なかにはブラジルの法律家も加盟しています。
当協会はドイツと日本のあらゆる分野の法律家同士の協力を促進すると同時に、それぞれの司法制度に対する相互理解を深めてもらうことを目的としています。これまでのようなドイツ国内法を日本に紹介するだけの一方通行ではなく、関心を持つドイツやその他の欧米の法律家に日本国内法を深く理解してもらえるような、より広い「アウトバーン」を作っていきたいと考えております。したがって日本と欧州での特許訴訟をテーマとしたこのシンポジウムは、まさに独日法律家協会の趣旨に沿ったものであります。

独日法律家協会 会長
ヤン・グロテア博士
3. プログラム
※各部の講演者の資料(PDF)は「5.参考資料」の「1.シンポジウムに関する情報」にリンク一覧がありますので、ダウンロードしてご利用ください。
| 10時00分 | 開会 | ||||||||||||
| 10時05分-10時20分 | 開会の挨拶 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 10時20分-12時30分 | 第1部 講演の部 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| 12時30分-14時00分 | 休憩 | ||||||||||||
| 14時00分-15時30分 | 第2部 統一特許裁判所に関する模擬裁判と解説 | ||||||||||||
|
テーマ: 欧州統一特許裁判所と無効の抗弁
|
|||||||||||||
| 15時30分-16時00分 | コーヒーブレイク | ||||||||||||
| 16時00分-18時00分 | 第3部 パネルディスカッション | ||||||||||||
|
16時00分-17時00分
17時00分-18時00分
|
|||||||||||||
| 18時00分 | 閉会 | ||||||||||||
|
※日英同時通訳
4. 講演者情報
- 講演者情報の目次
- ごあいさつ
- 裁判所
- 特許庁
- 大学
- 企業
- 弁護士
- 弁理士
ごあいさつ

小宮 義則 (こみや よしのり)
特許庁 長官
| 1984年 | 3月 | 東京大学経済学部経済学科卒業 |
| 1984年 | 4月 | 通商産業省入省、生活産業局総務課総括係、立地公害局工業用水課 総括係長、基礎産業局化学製品課総括係長を経て、 |
| 1989年 | 6月 | 米国留学(NorthEast Asia-U.S. Forum, Stanford Univ.) |
| 1990年 | 5月 | 通商政策局国際経済部国際経済課GATT室長補佐(企画班長) |
| 1991年 | 4月 | 長崎県経済部企業振興課長 |
| 1993年 | 6月 | (通商産業省)生活産業局繊維製品課総括課長補佐 |
| 1996年 | 2月 | 環境立地局立地政策課総括課長補佐 |
| 1997年 | 6月 | 基礎産業局総務課総括課長補佐(法令審査委員) |
| 1998年 | 6月 | 在大韓民国日本国大使館一等書記官 |
| 2001年 | 1月 | 在大韓民国日本国大使館参事官 |
| 2001年 | 6月 | (経済産業省)経済産業政策局知的財産政策室長 |
| 2004年 | 6月 | 製造産業局産業機械課長 |
| 2005年 | 8月 | 製造産業局ロボット産業室長(併任) |
| 2005年 | 10月 | 経済産業大臣秘書官(事務取扱) |
| 2006年 | 7月 | 経済産業政策局産業資金課長 |
| 2008年 | 7月 | 内閣官房内閣参事官(副長官補付) |
| 2010年 | 7月 | (経済産業省)資源エネルギー庁総合政策課長 |
| 2011年 | 7月 | 大臣官房審議官(経済社会政策担当) |
| 2012年 | 7月 | 株式会社産業革新機構 専務執行役員 |
| 2014年 | 7月 | 内閣府 大臣官房宇宙審議官 宇宙戦略室長 |
| 2016年 | 4月 | 内閣府 宇宙開発戦略推進事務局長 |
| 2016年 | 6月 | (経済産業省) 特許庁長官 |
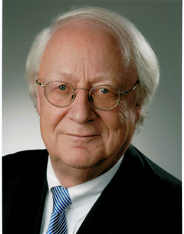
ヤン・グロテア
独日法律家協会 会長
| 1945年7月11日 | ハノーファー生まれ |
| 1965年-1969年 | 大学にて法律・経済を専攻(ハンブルグ) |
| 1970年-1974年 | 学術研究助教授(民事・労働法) |
| 1974年-1975年 | Scherzberg & Undritz法律事務所(現White & Case, Feddersen法律事務所)所属弁護士 |
| 1975年 | ハンブルグ地方裁判所判事 |
| 1978年-1980年 | 法務大臣付き報道官(ハンブルグ) |
| 1980年-1982年 | ハンブルグ区裁判所所長補佐官(管理任務) |
| 1982年 | ハンブルグ租税裁判所判事 |
| 1997年-2010年 | ハンブルグ租税裁判所所長 |
| 1992年-2005年 | ドイツ裁判官協会理事会メンバー |
| 1992年-2005年 | 国際裁判官協会ドイツ代表 |
| 1995年- | 独日法律家協会会長 |
裁判所

ペーター・マイアー=ベック
ドイツ連邦最高裁判所 第10民事部総括判事
| ペーター・マイアー=ベック氏は1955年生まれのドイツ人で、ボン大学とフライブルク大学で法学を学び、1980年に法学位を取得し、1984年にフライブルク大学から法学博士号を取得した。1984年には弁護士として活動したが、1985年から1993年の間はデュッセルドルフ地方裁判所、高等地方裁判所において裁判官として勤務した後、デュッセルドルフ地方裁判所第4民事部(ノルトライン=ヴェストファーレン州特許侵害裁判所)首席裁判官に就任した。マイアー=ベック氏は2000年に連邦裁判官及び連邦裁判所の一員に任命され、再び特許及び競争(独占禁止)の案件を担当することとなった。連邦裁判所競争法部門に在籍したまま、2010年11月からは第10民事部総括判事(特許部門)を務めている。マイアー=ベック博士は長年にわたって知的財産権法、特に特許法について教鞭を執っている。2005年2月、デュッセルドルフ大学より名誉教授の称号を授与された。 |

クラウス・グラビンスキー
ドイツ連邦最高裁判所 判事
| クラウス・グラビンスキー博士は2009年に連邦通常裁判所裁判官に任命された。特に特許紛争の案件を管轄する第10民事部に配属されている。これより以前にはデュッセルドルフ地方裁判所にある2つの特許訴訟部の一方の首席裁判官(2001年から2009年)を務めたほか、デュッセルドルフ控訴裁判所の裁判官(2000年から2001年)、連邦通常裁判所の法律研究者(1997年から2000年)、デュッセルドルフ地方裁判所の裁判官(1992年から1997年)を歴任した。 同博士はトリーア、ジュネーブ及びケルン大学で法律を学び、欧州特許条約に関する意見書(Benkard, Europaisches Patentubereinkommen, 2nd edition)及びドイツ特許法に関する意見書(Benkard, Patentgesetz, 11th edition)の作成にも携わった。特許法、民事訴訟及び国際私法に関する論文も多数執筆している。 欧州統一特許裁判所(UPC)準備委員会に対して助言を行う専門家パネルの一人で、それ以前にはUPC手続規則起草委員会の一員を務めた。国内外で特許法に関して積極的に講演を行っている。 |

ベアーテ・シュミット
ドイツ連邦特許裁判所 長官
| 1975年 | ヴュルツブルク大学法学部卒業 |
| 1982年 | 第2次国家試験合格 |
| 1982年 | アシャッフェンブルク地方裁判所判事(刑事法)就任 その後は民事法担当となり、最終的には同裁判所検察官として勤務 |
| 1986年 | 連邦司法省へ出向。著作権法担当官、司法省事務次官付補佐官(1991年-1994年)等のポストを歴任 |
| 1994年 | 連邦特許裁判所判事に任命(商標権担当委員会に配属) |
| 1997年 | ドイツ特許商標庁人事部部長に任命 |
| 2001年 | ドイツ特許商標庁商標部部長に任命 |
| 2006年 | スペイン、アリカンテの欧州共同体商標意匠庁(OHIM)(現 欧州連合知的財産庁(EUIPO))商標部部長に就任、その後、取消訴訟部部長就任 |
| 2011年 | 連邦特許裁判所長官、第1無効部門首席裁判官に任命される |

設樂 隆一 (したら りゅういち)
知的財産高等裁判所 所長
| 1975年に東京大学法学部を卒業。1979年に東京地方裁判所判事補(知財部)となり,その後,東京地方裁判所判事(知財部),大阪地方裁判所判事,東京地方裁判所判事(知財部),さいたま地方裁判所判事を経て,2001年に東京高等裁判所判事(知財部),2005年に東京地方裁判所部総括判事(知財部)となった。その後,2008年に東京高等裁判所判事,2009年に新潟地方裁判所長となり,2011年には東京高等裁判所部総括判事,2013年には知的財産高等裁判所部総括判事を歴任し,2014年6月から知的財産高等裁判所長となっている。知的財産権訴訟に関する著書を多数執筆している。 |

清水 節 (しみず みさお)
知的財産高等裁判所 部総括判事
|
1977年に東京大学法学部を卒業。1979年に横浜地方裁判所判事補となり,その後,東京家庭裁判所判事,東京国税不服審判所審判官などを経て,1996年に東京高等裁判所判事(知財部)となる。那覇地方裁判所部総括判事,東京高等裁判所判事(知財部)を経て,2004年に東京地方裁判所部総括判事(知財部)となり,その後,知的財産高等裁判所判事,徳島地方家庭裁判所長を経て,2013年に知的財産高等裁判所部総括判事となり,現在に至る。 我が国の知的財産権訴訟に関して,多数の論文を執筆するほか,国内外で講演を行っている。 |

東海林 保 (しょうじ たもつ)
東京地方裁判所 部総括判事
| 1983年に明治大学法学部卒業。1989年に東京地方裁判所判事補。その後,1991年に岐阜地方裁判所判事補,1994年に釧路地方裁判所北見支部判事補,1996年に東京家庭裁判所判事補,1999年に那覇地方裁判所沖縄支部判事,2002年に東京地方裁判所判事(知財部),2006年に函館地方裁判所部総括判事,2009年に知的財産高等裁判所判事を経て,2012年に東京地方裁判所部総括判事(知財部)となり,現在に至る。 |

沖中 康人 (おきなか やすひと)
東京地方裁判所 部総括判事
| 1990年 | 東京大学法学部卒業 |
| 1992年 | 東京地裁判事補任官 |
| その後,釧路地家裁,東京地裁,那覇地裁沖縄支部,東京高裁・知財高裁,名古屋高裁金沢支部,法務省,横浜地裁の勤務を経て,2015年から東京地裁(知財部)部総括判事の現職にある。 知財訴訟については,1997年から2001年まで東京地裁知財部,2003年から2006年まで東京高裁知財部・知財高裁,2015年から現在まで東京地裁知財部において担当している。 |
特許庁

フーベルト・フックス
欧州特許庁 審査長
| フーベルト・フックス氏は、フランスで機械と電子工学の工学修士号を取得。その後、欧州特許庁ベルリン支局で特許審査官として17年間勤務し、2002年からライン管理部門の役職に就く。 現在は、医療技術、応用化学、バイオテクノロジー、物理学の技術分野を管理し、氏の下で特許審査官は、特許手続(サーチ、実体審査、減縮、取消および異議申立て)のあらゆる局面に対応する。 ライン管理業務のほか、ここ数年は、人事、品質、特許手続などさまざまな部門を横断的に統括しており、2012年からはベルリン支局副サイトマネージャーの役職に就いている。 フーベルト・フックス氏は、いわゆる地域産業財産権プログラム(RIPP)や、欧州特許庁がほかの国の特許庁と組織する国際協力プログラムの枠組みの中でのさまざまな研修活動で、トレーナーや講師を務めることもある。 |

嶋野 邦彦 (しまの くにひこ)
特許庁 審判部長
| 早稲田大学大学院理工学研究科修士課程修了 | ||
| 昭和60年 | 4月 | 特許庁入庁(審査第五部制御発電) |
| 平成1年 | 4月 | 審査官昇任(審査第五部制御発電(自動制御)) |
| 平成4年 | 6月 | 産業政策局総務課知的財産政策室調査班長 |
| 平成6年 | 2月 | 審査第二部調整課審査基準室長補佐 |
| 平成7年 | 1月 | 外務省経済局国際機関第一課長補佐 |
| 平成9年 | 2月 | 総務部秘書課長補佐 |
| 平成10年 | 10月 | 審判部審判官昇任(第16部門) |
| 平成12年 | 1月 | 審査第二部調整課長補佐 |
| 平成15年 | 10月 | 総務部技術調査課大学等支援室長 |
| 平成17年 | 1月 | 内閣官房知的財産戦略推進事務局参事官 |
| 平成19年 | 1月 | 特許審査第四部上席総括審査官(伝送システム) |
| 7月 | 特許審査第一部調整課審査推進室長 | |
| 平成20年 | 7月 | 総務部企画調査課長 |
| 平成22年 | 10月 | 特許審査第四部上席審査長(伝送システム) |
| 平成24年 | 7月 | 特許審査第一部調整課長 |
| 平成25年 | 7月 | 審査第四部長 |
| 平成27年 | 7月 | 審判部長(現職) |

丹治 彰 (たんじ あきら)
特許庁 首席審判長
| 学歴 | |
| -1983.03. | 東北大学 大学院工学研究科 博士(前期)課程 |
| 職歴 | |
| 1983.04. | 特許庁入庁 |
| 1987.04. | 審査官昇任(審査第五部 情報処理) |
| 1994.02. | 一等書記官(在インド日本国大使館、ニューデリー) |
| 1997.04. | 審判官(審判部第12部門) |
| 2004.07. | 上席総括審査官(特許審査第四部 記憶管理) |
| 2007.08. | 審査監理官(特許審査第四部 情報記録) |
| 2008.07. | 上席審査長(特許審査第四部 伝送システム) |
| 2010.10. | 首席審査長(特許審査第四部) |
| 2011.10. | 裁判所調査官(最高裁判所及び知的財産高等裁判所) |
| 2014.10. | 部門長(審判部第32部門) |
| 2015.04. | 首席審判長 |

千壽 哲郎 (せんじゅ あきお)
特許庁 審判長
| 1988年 | 東京大学農学部卒業、特許庁入庁 |
| 1994年 | 通商産業省通商政策局APEC推進室長補佐 |
| 2001年 | 総務部技術調査課長補佐(技術動向班長) |
| 2006年 | 特許審査第二部主任上席審査官 併)ハイブリッド自動車審査プロジェクト・リーダー |
| 2008年 | 特許審査第二部上席総括審査官 |
| 2011年 | 東北大学大学院法学研究科教授 併)産学連携推進本部知的財産審査委員会委員 |
| 2013年 | 特許審査第二部審査長 |
| 2014年~ | 審判部審判長 平成27年度審判実務者研究会特許機械分野検討メンバー 平成28年度弁理士試験委員 |
大学

高林 龍 (たかばやし りゅう)
早稲田大学 教授
| 1976年に早稲田大学法学部を卒業。1978 年に東京地方裁判所判事補となり,その後,那覇地方裁判所判事補,東京地方裁判所(知財部)判事補,松山地方裁判所判事,1990年最高裁判所調査官(知財事件等担当)を経て,1995年に退官し,早稲田大学法学部助教授、1996年同教授となり,以後現在に至るまで知的財産法の教育・研究に従事している。現在,日本工業所有権法学会理事長,著作権法学会理事、産業構造審議会知的財産分科会特許制度小委員会委員長。著書として,標準特許法〈第5版〉(有斐閣),標準著作権法〈第2版〉(有斐閣),知的財産に携わる人のための標準民事手続法(発明推進協会),そのほか知的財産法に関する論文を多数執筆している。 |
企業

長澤 健一 (ながさわ けんいち)
キヤノン株式会社 常務執行役員 知的財産法務本部長
| 1981年 | 3月 | 同志社大学工学部電子工学科 卒業 |
| 1981年 | 4月 | キヤノン株式会社入社 |
| 1994年 | 7月 | 知的財産法務本部 特許技術センター 特許第四部 特許第42課 課長 |
| 1999年 | 1月 | 知的財産法務本部 GIP管理室 室長 |
| 2000年 | 1月 | 知的財産法務本部 知的財産業務センター GIP部 副部長 |
| 2000年 | 10月 | キヤノンヨーロッパN.V.出向 |
| 2001年 | 7月 | キヤノンヨーロッパLtd.出向 Senior General Manager |
| 2006年 | 3月 | 知的財産法務本部 知的財産第二技術センター センター所長 |
| 2008年 | 10月 | キヤノンU.S.A.,Inc.出向 Senior Director |
| 2010年 | 3月 | 知的財産法務本部 副本部長 |
| 2010年 | 4月 | 執行役員 知的財産法務本部長(現在) |
| 2012年 | 3月 | 取締役 |
| 2016年 | 3月 | 常務執行役員(現在) |
弁護士

クリストフ・カール
バーデーレ・パーゲンベルク法律事務所 弁護士
| クリストフ・カール博士は特許訴訟及び出願を専門としており、特にコンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信の技術分野を専門としている。またライセンス、職務発明法、著作権法についても助言を行う。 カール博士はドイツ地方裁判所及び控訴裁判所での特許侵害訴訟手続きにおいてクライアントの代理人を務めるほか、欧州特許庁、ドイツ特許商標庁、ドイツ連邦特許裁判所、ドイツ連邦最高裁判所での特許無効訴訟手続きにおいても代理人を務める。特許出願業務のなかでも、カール博士が重点を置く分野の1つとしてソフトウェア及びコンピュータ関連発明の特許性が挙げられる。カール博士のクライアントにはコンピュータ、コンピュータネットワーク、通信、金融サービスの分野においてアメリカを代表する企業や、日本の大手コンピュータゲームメーカーのほか、中小のドイツ企業及び国際企業がある。 ドイツ及びアメリカ、ニューヨーク州で弁護士として業務を行うことが認められた資格を保持しており、コンピュータ科学者、ドイツ弁理士、欧州弁理士でもあるカール博士は、法律面及び技術面の両方から案件を処理することが出来る。カール博士はミュンヘン知的財産法センター(MIPLC)及びリエージュ大学(ベルギー)において特許法を教えている。 |

クリスチャン・レデラー
テイラー・ヴェッシング法律事務所 弁護士
| クリスチャン・レデラー氏はテイラー・ヴェッシング法律事務所ドイツ特許グループの責任者であり、同社ミュンヘン事務所に在籍している。 同氏は特許法に関連する案件について国内外のクライアントに助言すると同時に代理人を務めている。海外や管轄区域をまたぐ訴訟の管理及び調整等の、特許訴訟(特許侵害及び特許無効訴訟)を専門としている。 レーデラー氏はドイツ国内の全ての特許裁判所(地方裁判所、控訴裁判所、連邦特許裁判所、連邦最高裁判所)においてクライアントの代理人を務めている。日本のクライアントに特に慣れているほか、日本の特許法にも精通している。1996年にミュンヘンの法律事務所でキャリアを開始後、同事務所の知的財産権業務部門のコーディネーターに就任。その後2003年8月にテイラー・ヴェッシング法律事務所にパートナーとして加わった。同氏はミュンヘンで第一次国家試験を1992年に、第二次国家試験を1996年に合格している。1994年に法学博士号を取得している。 ドイツ産業権保護・著作権協会(GRUR)、国際知的財産保護協会(AIPPI)の会員である。また、独日法律家協会(DJJV)ではバイエルン州スポークスマンを務めるほか、独日協会(DJG)の会員でもある。 |

ディルク・シュスラー=ランゲハイネ
ホフマン・アイトレ法律事務所 弁護士
| ディルク・シュスラー=ランゲハイネ博士はドイツの弁護士で、欧州において知的財産権を専門とするホフマン・アイトレ特許法律事務所の特許訴訟・ライセンス部門を率いている。同博士はドイツのボン大学で法律、政治、日本語、日本文化を学んだ後、法学博士号を取得した。博士論文のテーマは日本における損害賠償請求訴訟であった。日本に2年間留学したことがあり、そのうち1年間は国際交流基金の研究員として神戸大学法学部に研究生として在籍した。弁護士としての最初の数年をデュッセルドルフの総合法律事務所のジャパンデスクで過ごした後、2004年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に加わった。 シュスラー=ランゲハイネ博士の主な専門分野は特許訴訟及びライセンス関連法である。同博士はドイツでは特許訴訟代理人であり、管轄区域をまたぐ欧州での特許関連訴訟のまとめや調整にあたっている。シュスラー=ランゲハイネ博士は日本企業にドイツ及び欧州の法律について助言を行い(日本語で)、欧州企業に日本の法律について助言を行うことを得意としている。同博士は「日本と欧州における特許実務―グントラム・ラーン博士記念論集」概論の共著者であるほか、ドイツ、欧州、そして日本の特許及びライセンス関連法についてもいくつかの著書がある。 |

三村 量一 (みむら りょういち)
長島・大野・常松法律事務所 弁護士
| 1977年東京大学法学部卒業。1979年~2009年裁判官。最高裁判所調査官、東京地方裁判所部総括判事(知的財産部)、知的財産高等裁判所判事等を歴任。2009年弁護士登録(第一東京弁護士会)、長島・大野・常松法律事務所入所。 裁判官として、長期にわたって知的財産権訴訟に携わったほか、知的財産法関係の審議会の委員を務め、多数の学術論文を発表する等、特に知財法関連分野に精通した法律実務家として知られる。 裁判官時代の豊富な経験をもとに、特許・実用新案、意匠、商標、著作権、不正競争防止法関係の事案を中心に、法的助言から訴訟対応まで幅広くサービスを提供する。とりわけ、特許権、商標権、著作権等の侵害訴訟や、職務発明対価請求訴訟等における対応につき、豊富な知識経験を有する。また、ドイツ法の知識も豊富で、ドイツ関係の案件も得意とする。 |

片山 英二 (かたやま えいじ)
阿部・井窪・片山法律事務所 弁護士
| 京都大学工学部、神戸大学法学部卒業。企業勤務の後1984年弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所。1988-1990年欧米留学研修、1989年米国ニューヨーク州弁護士登録、1991年よりパートナー。日弁連知的財産センター委員長、日本国際知的財産保護協会(AIPPI・Japan)会長などを歴任、ミュンヘン知財法センター(MIPLC)教授。知財訴訟、特に数多くの国際特許訴訟に携わる。著書に”Japanese Patent Litigation” West 2012などがある。 |
弁理士

トーステン・バウシュ
ホフマン・アイトレ法律事務所 弁理士
| トーステン・バウシュ博士はドイツ及び欧州の弁理士である。化学及びバイオテクノロジー分野の特許を専門としており、そのなかでも訴訟(国内外)、異議申立て、査定系審判、リーガルオピニオンに強い。主に得意とするのは製薬、ポリマー、免疫学の分野である。 バウシュ博士はミュンヘン工科大学より化学博士号を取得している。1992年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に入所後、1995年にドイツの弁理士となり、その翌年に欧州弁理士の資格を取得した。 バウシュ博士は拡大審判部を含む欧州特許庁審判部、ドイツ連邦特許裁判所、ドイツ連邦裁判所、ドイツ侵害裁判所にて審議された多くの注目を集めた案件を担当した経験を持つ。また、欧州裁判所において補充的保護証明書関連案件の代理人を務めたことがある。 バウシュ博士はドイツ連邦特許裁判所及び連邦裁判所において出された特許無効判決の例を集めた「Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen」誌の編集者を務めている。これまでに著名なジャーナル上でドイツ及び欧州の特許法に関して多数の論文を執筆しており、日本で発行されている「Patents and Licensing」誌にも掲載されたことがある。また、国内外の会議において積極的に講演を行っている。 |

アンドレアス・シュテファール
ホフマン・アイトレ法律事務所 弁理士
| アンドレアス・シュテファール博士は欧州登録代理人及びドイツの弁理士であり、ミュンヘンに本拠地を置くホフマン・アイトレ特許法律事務所のバイオテクノロジー業務部門のパートナーの1人である。シュテファール博士は生物学の基礎をウィーン大学(オーストリア)及びマンチェスター大学(英国)で学んだ。ドイツ、ミュンヘンのマックス・プランク神経生物学・精神医学研究所で行った神経免疫学分野の実験研究に基づいた博士号を有する。博士研究員としてウィーン大学でさらに科学研究を続けた後、格付機関のアナリスト、バイオテクノロジー分野の新興企業融資を専門としたベンチャーキャピタルの投資マネージャーとして民間企業での経験を積んだ。その後2003年にホフマン・アイトレ特許法律事務所に加わり、弁理士として訓練を受けた。アンドレアス・シュテファール博士の主な取り扱い分野は、バイオテクノロジー分野での特許出願や特許係争業務の全ての側面を網羅している。また博士は、FTO及び権利侵害についての助言等、個別に一般的な助言・意見を行っている。欧州特許庁での訴訟手続のほか、ドイツ国内の裁判所での権利侵害や特許の有効性を争う訴訟手続においてクライアントの代理人を務めている。特許法関連の問題をテーマとしたセミナーで定期的に講演を行っている。 |

奥山 尚一 (おくやま しょういち)
久遠特許事務所 弁理士
| 弁理士。日本弁理士会元会長。久遠特許事務所代表。早稲田大学理工学部卒、シカゴ大学大学院化学科博士課程修了。日本国際知的財産保護協会(AIPPI JAPAN)副会長。現在、内閣府知的財産戦略推進本部 有識者本部員を務める。2003年に産業財産権制度功労者として特許庁長官表彰、2011年にAIPPI よりAward of Merit、2013年にはthe American Inns of CourtよりAward of Distinguished Service Medalをそれぞれ受賞。著書に『Patent Infringement in Japan』(特許庁、2000年、2007年、2016年)、『特許の英語表現・文例集』(講談社サイエンティフィク、2004年、2016年)他多数。 |

加藤 志麻子 (かとう しまこ)
阿部・井窪・片山法律事務所 弁理士
| 阿部・井窪・片山法律事務所パートナー弁理士。早稲田大学理工学部材料工学科卒業。審査官、審判官として特許庁に勤務し(1988-2006)、1998年には人事院留学で、ヨーロッパ特許庁及びドイツ特許庁に派遣される。東京地方裁判所調査官(2002-2005)を経て、2006年に弁理士登録し、阿部・井窪・片山法律事務所に入所。現在、主として特許権侵害訴訟及び無効審判に従事している。2013年に、デュッセルドルフ高等裁判所のThomas Kuhnen 判事の下でドイツの特許権侵害訴訟について学ぶ。AIPPI、アジア弁理士協会(APAA)、独日法律家協会(DJJV)、VPP(Vereinigung von Fachleuten des Gewerblichen Rechtsschutzes)会員。最近の論文として、「日本は魅力的な訴訟提起地になれるか?-ドイツにおける特許侵害訴訟の現状から見た日本の可能性-」AIPPI Vol.60 No.1 (2015年1月号)、「ドイツにおける最近のクレーム解釈及び均等論について」パテント Vol.68 No.1 (2015年1月号)(共著)、「進歩性の判断-合理的かつ予見性の高い判断のために-」設樂隆一他編『現代知的財産法 実務と課題 飯村敏明先生退官記念論文集』発明推進協会(2015年7月)などがある。 |
5. 参考資料
1. シンポジウムに関する情報
(1)全体資料
(2)基調講演
- 設樂隆一所長(PDF:750KB)
- ペーター・マイアー=ベック第10民事部総括判事(PDF:360KB)
- 嶋野邦彦審判部長(PDF:1.19MB)
- ベアーテ・シュミット長官(PDF:742KB)
- フーベルト・フックス審査長(PDF:344KB)
(3)統一特許裁判所に関する模擬裁判と解説
(4)パネルディスカッション:テーマ1
(5)パネルディスカッション:テーマ2
2. 欧州の特許に関する裁判所についての情報
欧州統一特許裁判所ウェブサイト(英語)
https://www.unified-patent-court.org/(外部サイトへリンク)
ドイツ連邦最高裁判所ウェブサイト(英語)
https://www.bundesgerichtshof.de/EN/Home/homeBGH_node.html(外部サイトへリンク)
欧州知的財産ニュース
https://www.jetro.go.jp/world/europe/ip/(外部サイトへリンク)
3. 均等論に関する判決
平成27年(ネ)第10014号(知的財産高等裁判所大合議)
http://www.ip.courts.go.jp/hanrei/g_panel/(外部サイトへリンク)
平成6年(オ)第1083号(最高裁判所第三小法廷)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52790(外部サイトへリンク)
4. 審判実務者研究会
審判実務者研究会報告書
http://www.jpo.go.jp/shiryou/toushin/kenkyukai/sinposei_kentoukai.htm
5. 関連団体ウェブサイト
特許庁
http://www.jpo.go.jp/indexj.htm
独日法律家協会
http://www.djjv.org/index.php/en/(英語)(外部サイトへリンク)
http://www.djjv.org/index.php/de/(ドイツ語)(外部サイトへリンク)
日本弁護士連合会
https://www.nichibenren.or.jp/(外部サイトへリンク)
弁護士知財ネット
http://www.iplaw-net.com/(外部サイトへリンク)
日本弁理士会
https://www.jpaa.or.jp/(外部サイトへリンク)
日本知的財産協会
http://www.jipa.or.jp/(外部サイトへリンク)
日本国際知的財産保護協会
http://www.aippi.or.jp/(外部サイトへリンク)
法務省
http://www.moj.go.jp(外部サイトへリンク)
[更新日 2017年1月19日]