ホーム> お知らせ> 採用情報> 総合職・一般職> 商標審査官 採用情報> 商標審査官インタビュー
ここから本文です。
商標審査官インタビュー
商標審査業務
毎日が学びの連続(2024年入庁/食品)

私は約1年間、審査業務に携わってきました。まだまだ知らないことばかりだな、と感じる毎日ですが、常に新たな学びがあり、とても楽しく業務を行っています。
社会における言葉やマークの使われ方は常に変化していますし、審査判断は刻々と積み上がっていき、商標制度は変化していきます。これらの観点を踏まえて審査をする必要がありますから、商標の審査に関する知識の習得に終わりはなく、常に学び続ける必要があると感じています。それがこの仕事の面白さだと思いますし、これからどんなことを学べるのか、ワクワクします。
入庁前は、仕事内容について、出願人の方と接することもなく、庁内で黙々と審査をこなすイメージをもっていました。しかし、実際は、出願人の方と電話や面接をする機会や、出願人である企業との意見交換会に参加させていただく機会があります。出願人の方が抱く疑問や、審査に求めていることについて、生の声を聞くことができ、自分の審査が大きな影響を与えていることを再確認するとともに、普段とは異なる視点からの学びを得ています。登録できない理由があるときは、その理由や解消する方法を文書で伝える必要がありますが、出願人の方にとってわかりやすく、納得感のある文書を作成することを心がけています。
様々な観点を踏まえて審査判断をすることも、わかりやすく納得感のある文書を作成することも、難しく、悩むことは多いですが、指導審査官をはじめ、周囲の方々にたくさん助けていただきながら業務を進めています。相談のしやすい雰囲気で、皆さん丁寧に助言してくださる、とても温かい職場です。このパンフレットを読んでいる皆さんとも一緒に働けることを楽しみにしています。
様々な経験を糧に新たな分野に挑戦(2009年入庁/国際商標登録出願)

私は現在、海外から日本へ出願される商標の審査を担当しています。商標権は国ごとに保護されるので、日本でも商標権を得たい事業者は、日本特許庁に出願する必要があります。海外からの出願には、複数国に一括して出願するマドリッド協定議定書に基づく国際商標登録出願(マドプロ出願)と、国ごとに直接出願する方法があり、私が所属しているマドプロ審査室ではマドプロ出願された商標の審査を担当しています。
日本へのマドプロ出願は年間約1.6万件に上り、マドプロ審査室では、総勢約25名の審査官(補)で審査を行っています。商標はビジネスにとって重要な権利ですので、スムーズかつスピーディーに審査できるよう心がけています。
マドプロ出願の審査には、海外の商標ならではの事情があります。まず、商標が日本語ではないので、商標が「単に商品・サービスの品質等を表すに過ぎないもの」ではないか、特に気をつけています。例えば、産地等を表す地名は、単に商品・サービスの産地等を表示するに過ぎないものですから、原則商標登録はできませんが、海外の地名はその地名を知らなければ見落とす可能性が高まります。業界内の流行語なども同様なので、普段から海外の文化や流行にアンテナを張るよう心がけています。
また、手続きの書類は原則英語なので、不備を修正する補正も英語でのやりとりが多く、コミュニケーションに気を遣う場面も多いです。それでも、出願人や代理人と丁寧にやりとりを重ねて、無事に登録に至ったときは達成感がありますし、審査を通して仮想通貨や仮想空間サービスのような世界の新しいトレンドにいち早く触れられるのも商標審査という仕事の面白いところかもしれません。
ぜひ将来、この記事を読んでくださっている皆さんと一緒に商標の審査に携われたら嬉しいです!
商標行政事務
商標を通じて地域ブランドの保護及び地域活性化を支援(2019年入庁/地域ブランド推進室)
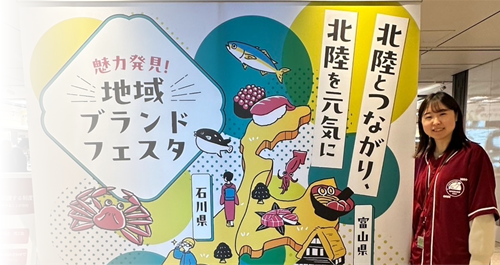
みなさん、「地域ブランド」とはどういうものか、ご存じでしょうか?「地域ブランド」とは、商品の品質をはじめ、他の地域にない独自性、こだわり、地域自体に感じる魅力、歴史・文化などさまざまな要素を活かしたものです。そして、「地域ブランド」のブランド力を高めていくためには、ブランド名について商標登録をし、安心してブランド名を使用できる環境を整えることが有効です。
特許庁では、地域ブランドを適切に保護することにより、地域経済の活性化を支援することを目的として、2006年に地域団体商標制度を創設しました。
地域ブランド推進室は、この地域団体商標制度に関する業務を所管する部署です。例えば、制度説明会の実施、これから地域団体商標の取得を検討している団体からの個別相談対応、地域団体商標の審査支援、制度普及用のパンフレットの作成など、制度の普及啓発や審査に関する様々な業務を行っています。制度説明のご要望をいただいた際は、現地へ訪問して説明を行います。
全国を飛び回って、多種多様な事業者の方と対話することができるのは、地域ブランド推進室の魅力の一つです。
令和6年度には、地域団体商標制度のさらなる普及を目指し、地域団体商標の権利者を出店者とする物販イベントを初めて開催しました。出店団体からは「多くの方にご来場いただき、予想を上回る成果が得られた」という嬉しいお声をいただくことができ、大きな達成感とともに、多くの学びを得ることができました。商標審査の経験を生かしつつ、地域活性化の支援に携われるように、商標審査官はやりがいのある様々な業務がありますので、ぜひ興味をもっていただけたら嬉しいです。
商標という専門性を軸に国際業務に携わる(2018年/国際協力課)
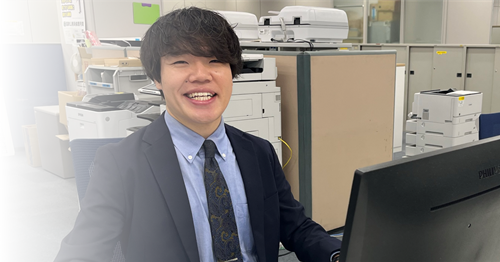
私は現在、商標審査業務を離れ、国際協力課という部署で商標に関する国際業務を担当しています。商標分野における海外との窓口的な役割を果たしており、海外知財庁との会合の開催や協力プロジェクトの推進、他国の商標制度や商標問題に関する情報収集など、幅広い業務を行っています。
商標分野においては、二国間・複数国間と意見交換の場が充実しており、商標という大きなテーマのもと、各国の最新の施策や審査運用に関する情報交換、及び、共通の課題の解決に向けた議論等を行うための国際会合が年度を通じて数多く開催されています。2024年12月に箱根で開催したTM5年次会合では、海外知財庁や国内外のユーザーを含めた関係各所との調整に苦労しながらも、共通の目標に向けて海外の方と協力するという国際業務の醍醐味を感じることができました。
近年、有名な地名やブランドなどの商標が他国において無関係な第三者により無断で商標出願・登録される、いわゆる「悪意の商標出願」が国際的な問題となっており、日本の地名やブランドも例外ではありません。商標の保護は国ごとの法律に基づくため、他国で商標を保護するには、その国での出願・登録が必要です。このような問題に対処するため、日頃から海外の情報を収集し、問題が発生した際に適切に対応することも重要な業務です。
このように商標審査官には、商標の審査業務だけでなく、商標という専門性を軸に国際的なフィールドで活躍するチャンスもあります。ぜひ、関心を持っていただけると嬉しいです。
将来の商標審査を支えるシステムを作っています(2007年/総務課情報技術統括室)

皆さんはプライベートでも様々な「システム」を利用されていると思います。スマホアプリや電子マネー、ゲームなど世の中の多くの商品・サービスで何らかのシステムが活用されています。一方で、そのシステムに不具合が生じた際や使い勝手について不満を覚えたこともあるでしょう。そして、そんなユーザーの声を反映して改善が行われたり、次のシステムが作られたりするのを見たこともあるのではないでしょうか。
商標審査業務においても、専用のシステムを活用して審査や案件管理を行っています。ただし、ずっと同じものを使い続けているのではなく、様々な理由で新規開発や改修がされています。その際、より良い商標審査システムとするためには、もちろんユーザーである商標審査官の意見が重要となります。
私は商標審査やいくつかの行政業務を経験し、現在は商標審査システムの運用や将来の開発・改造に関する業務を担当しています。なお、私自身は文系大学を出ており、プログラミングの知識などもほとんどありません。主な業務は、審査官の意見を集約し、開発・保守事業者との調整を行うというものになりますが、それにはどうしても審査官としての経験や業務知識が必要となります。
また、誰か一人が活躍しているのではなく、多くの関係者がそれぞれの知見を活かし、将来の審査業務をより円滑に進めるための審査システムの開発や、既存の審査システムの不具合対応に尽力しているというのも今の業務の特色です。
まずは、審査経験を積んでいただき、ゆくゆくは商標審査官の知見を活かして「将来の商標審査を支えるシステム」を作っていく。そんな業務を皆さんと一緒に担っていけることを楽しみにしています。
法律のエキスパートとして(2000年入庁/商標制度企画室)

商標制度企画室では、主として、制度(法律)の検討・見直しを行っています。
法律は全国民に影響するものですので、改正するには明確な理由が必要となります。この改正の理由を立法事実といい、具体的には、改正を求めるユーザの声や、諸外国では既に同様の改正がなされているが日本では未改正であること等を指します。
この立法事実を明確にするために、1年をかけて調査を行い、諸外国の商標制度を調べ上げ、ユーザに対するアンケートやヒアリングを実施します。調査結果を踏まえて、有識者の方々に議論いただくための会議(審議会)を開催し、法律改正のための具体的な条文案を作成します。条文案の作成にあたっては、商標法の数ある条文のどこをどのように変える必要があるのかを考える必要があるため、全ての条文について把握し、条文解釈やその根拠となる判決等についても通じている必要があります。条文案の作成が完了すると、内閣法制局による厳しい条文審査を受け、国会にて審議をいただき、ようやく法律案が成立します。その後も、法律を公布し、施行に向けて改正法の周知を行うとともに、審査に関連する条文の改正を行う場合は、審査基準の改訂も行います。
以上のプロセスは、短くとも2年はかかります。
現在、私はこのプロセスの調査の段階に携わっていますが、改正による様々な影響に思いを巡らし改正後の条文案を見据えながら、仕事をしております。
審査にとどまらない商標法全体についての知見や外国の商標法の知識を身に付け、幅広い専門性を身に付けたエキスパートとなるべく日々奮闘をしております。こうした仕事に魅力を感じる皆様、ぜひ商標審査官の門をたたいてみてください!
商標審査官の業務に少しでも興味を持たれた方は、ぜひ業務説明会にお越しください。
より詳しい情報を知りたい方は商標審査官採用パンフレット(PDF:12,510KB)をご覧ください。
[更新日 2025年6月13日]