ホーム> お知らせ> 採用情報> 総合職・一般職> 商標審査官 採用情報> 商標審査官のシゴト
ここから本文です。
商標審査官のシゴト
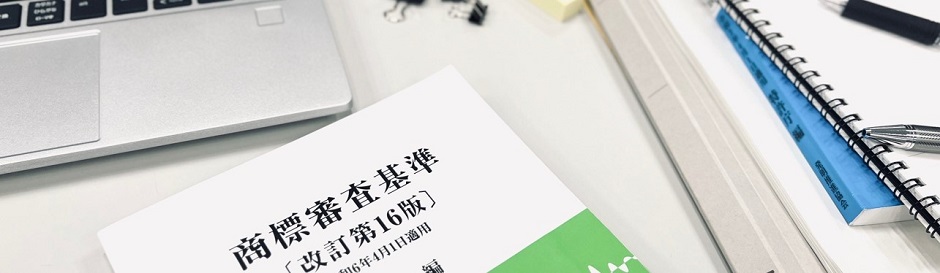
商標審査官のシゴトは大きく分けて「商標審査業務」「商標行政事務」「商標審判業務」の3種類です。
商標審査官のベースとなる業務は商標審査です。採用後は、審査官補の期間を経て、審査官に昇任します。
しかし、「審査官」といっても「審査」の仕事だけをしている訳ではありません。商標審査官として培った知識や経験などの専門性を活かして、企画立案業務、法律改正業務、国際業務など、商標に関する様々な「行政」分野に携わって働いています。
このように「審査業務」と「行政事務」を両輪とする「商標行政」全体の中心となって活躍しているのが「商標審査官」です。
商標審査業務

商標審査官は、特許庁に提出された商標の出願について、商標権を付与することができるか否かについて審査を行っています。
商標権を取得するためには、特許庁での商標登録が必要です。まずは、所定の様式に従って書類を作成し、特許庁に商標登録の申請(出願)をします。
特許庁では、「方式審査」(書式等の審査)をした後、商標登録すべきか否かの「実体審査」(内容の審査)を行います。この「実体審査」が私たち商標審査官の腕の見せ所です。
商標審査業務では、一人ひとりの審査官が様々な分野の商標の審査を担当しています。商標の審査には、法令・条約・審査実務等の高い専門知識のみならず、需要者・取引者の視点に立った考え方や、新しい商品・役務(サービス)への関心、業界のトレンドや専門用語に対する理解など、多岐にわたる知識や興味が重要になってきます。
商標行政事務
商標審査官は、商標審査業務の他、商標に関する知識や経験などの専門性をいかして、企画立案業務、法律改正業務、国際業務など商標に関する様々な「行政」分野に携わって業務を行っています。
国際業務 国際的な協力と商標制度の調和に向けて

インターネットの普及や経済のグローバル化が進み、日本の企業の経済活動は日本国内だけではなく海外でも行われるようになりました。それに伴い、商標の役割も国際的になっています。一方、商標制度は、その国の歴史、文化、経済状況などに合わせて、国ごとにそれぞれ多少異なった制度になっています。また、途上国などでは、商標制度が十分に整備されていない国もあります。
このような各国の商標制度やその運用について、国連の一機関である世界知的所有権機関(WIPO)における会議や、商標五庁(日本国特許庁、米国特許商標庁、欧州連合知的財産庁、韓国特許庁、中国国家知識産権局)の会合の場において、制度・運用の調和に向けた議論が盛んに行われています。私たち特許庁は、このような議論をリードし、また、商標制度の整備に向けた途上国への各種支援も行っています。
法改正業務 時代のニーズに合わせた制度作り
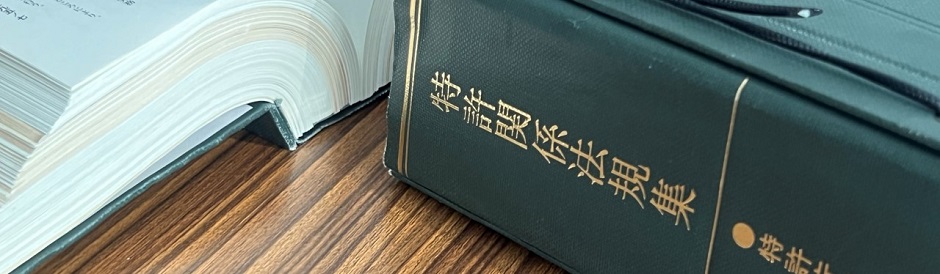
商標法などの法令や審査基準は、時代の変化やユーザーのニーズに応じて見直しが必要となります。これまでも、地域団体商標の保護や、「音」「動き」などの新しいタイプの商標の保護、コンセント制度の導入など、商標に関する様々なニーズに応じて商標制度の在り方の検討や見直しを行ってきました。
商標審査官は、こうした見直しの検討や法令改正の業務にも、商標のスペシャリストとして携わります。
1. 商標制度の改正
商標行政を担う部署では、商標制度に関するニーズや課題を調査し、より良い制度の実現を目指して検討を進めています。また、産業界の有識者や実務家等から構成される審議会の答申で示された方向性を踏まえ、必要な制度の改正も行っています。
2. 審査基準の改訂
商標審査基準は、「商標法」における審査に関する規定を運用する際の一般的な指針をまとめたものです。特許庁では、審査基準を策定・公開することにより、審査が適切かつ公平に行われるよう担保するとともに、有識者やユーザー等からの意見を踏まえた改訂も行っています。
システム関連業務

1. 商標制度を支える情報システム
特許庁では、1日当たり約460件(年間約17万件)の商標出願を受け付けていますが、その出願の受付から審査・登録・審判・公報の発行等に至るまで、商標制度に関する一連の業務を情報システムが支えています。
商標・特許・意匠の審査や手続業務毎のシステムからなる特許庁システムは、約70ものシステムより構成されており、近年のDXの推進やAI技術の発展等によって、情報システムの重要性は、ますます高まってきています。
2. 商標制度とAI
特許庁では、2021年度にAI技術を利用した先行図形商標検索システム(イメージサーチツール)に関する機械学習コンペティションを開催しました。コンペティションには、1400件を超える応募があり、入賞者のモデルは、特許庁で試験導入しているイメージサーチツールに搭載し、商標審査の品質向上を図っています。
商標審判業務

商標審査官は、一定期間の商標審査業務・ 商標行政事務を経験したのち、商標審判官へ昇任します。
出願人は、審査官の審査結果に不服がある場合、更なる審理を特許庁に対して求めることができます。これを「審判請求」といいます。審判請求されたときに活躍するのが「審判官」です。審判官は、3人(又は5人)で1組の合議体を構成し、審査官の審査結果の可否について審理し、結論を出します。
審判の結果について不服がある出願人は、知的財産高等裁判所(知的財産に関する訴訟を専門に扱う裁判所)へ出訴することができ、最終的には最高裁判所へ上告することもできます。訴訟になると、担当の審判官は、特許庁長官の「指定代理人」として法廷に立つことになります。
このような業務を行う「審判官」には、十分な審査経験と、所定の研修の修了など、より高度な専門性が求められます。
その他、商標審査官の業務については、「商標審査官採用パンフレット(PDF:12,510KB)」をご覧ください。
[更新日 2025年2月7日]