ここから本文です。
特許法等の一部を改正する法律について(報道発表)
平成14年4月
経済産業省
特許庁
1.法律改正の目的
情報技術の急速な進展に伴い、ネットワークを利用した新たな事業活動に、即応した法整備を行うとともに、こうした社会経済の変化を契機として、特許権等の効力範囲の在り方を見直す必要がある。
また、制度の国際調和、出願人の負担軽減、特許庁における審査の効率化の観点から、特許及び実用新案の出願方式の見直しを図る必要がある。
2.法律改正の概要
1.ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進
現行法は発明が「物=有体物」として活用されることを念頭に規定されているため、コンピュータ・プログラムそのもの(=無体物)について特許法で保護される範囲は必ずしも明らかではなかった。
ブロードバンド化に伴い、CD-ROM等の媒体に記録されない状態でのインターネットを介したプログラムの販売・流通が増大してきたことに鑑み、特許されたプログラム等をネットワーク上で無断で送信する行為等も特許権侵害に当たることを明確化する。
(特許法第2条第3項)
この法律で発明について「実施」とは、次に掲げる行為をいう。
一 物の発明にあつては、その物を生産し、使用し、譲渡し、貸し渡し、若しくは輸入し、又はその譲渡若しくは貸渡しの申出(譲渡又は貸渡しのための展示を含む。以下同じ。)をする行為
2.特許法の間接侵害規定の拡充
現行法は、特許権の侵害に使われる部品や材料を侵害者に供給する幇助的行為等を侵害行為に含めているが、対象を専用部品(その生産にのみ使用する物)に限定しているため、判例上も侵害が認められた事例は多くない。
このため、権利保護強化の観点から、悪意(特許発明であること及び侵害に用いられることを知りながら)で部品を供給する行為にまで間接侵害の成立範囲を拡大する。
3.ネットビジネスで使用される商標の信用保護強化
現行法は有体物に付される商標を念頭に置いて規定されている。近年、ネットビジネスの増大に伴い、インターネット上での商品やサービスの提供も普及しており、ユーザのパソコンや携帯電話の画面上で表示される商標(マーク)についても十分な保護が求められている。
そこで、ネットワークを介した商品流通、サービス提供及び広告等の事業活動において、画面上に表示して商標を使用する行為についても、商標権侵害となることを明確化する。
(注)商標とは、商品やサービスを識別するためのマークである。
例:「WALKMAN」「一太郎」(商品)、「JAL」(サービス)
4.出願人の負担軽減と迅速かつ適確な審査の促進
- 特許出願の方式を他の先進国や国際出願に整合させ、ユーザの出願準備の負担を軽減する。(明細書から特許請求の範囲を分離)
- 特許協力条約同盟総会の決議を受け、国際出願における国内書面の提出期間を一律30カ月に延長。また、翻訳文の提出に2ヶ月間の猶予期間を与え、翻訳文の質的向上を促し、ユーザの便宜及び審査の促進を図る。
(国内書面提出期間の延長等) - 出願人が有する先行技術文献情報を出願の際に審査官に開示することを制度化することにより、より迅速かつ適確な審査の実現を図る。
(先行技術文献情報の開示制度の導入) - 国際商標登録出願の個別手数料のうち、登録料に相当する額について、国内出願の場合と同様、出願が国内で登録査定された場合に支払えば良いこととする。(国際商標登録出願における個別手数料の分割納付)
参考
1.これまでの制度改正における取り組み
特許庁では、斬新な技術を権利化し、活用することにより、新たな研究開発への投資を行うという、「知的創造サイクル」の循環を促進すべく、以下の法改正を行ってきた。
こうした取組をさらに充実させるため、今回は、昭和34年の改正以来、抜本的な見直しが講じられてこなかった侵害行為に関する規定の改正を行う。
(1)権利の取得段階
- 審査請求期間の短縮、特許料金の引き下げ (平成11年)
- オンライン手続の拡大 (平成10年)
- 特許期間の延長、特許対象の追加、付与後異議制度の導入 (平成6年)
(2)権利の活用段階
弁理士の量的拡大と業務範囲の見直し (平成12年 弁理士法改正)
(3)権利の行使段階
- 侵害の立証等の容易化、判定制度の充実、刑事罰の強化(平成11年)
- 損害額の算定方式の見直し、侵害罪の非親告罪化 (平成10年)
2.経済構造改革における位置付け
(1)e-Japan重点計画 (平成13年3月29日 IT戦略本部決定)
|
4.電子商取引等の促進 (3)具体的施策 3.知的財産権の適正な保護及び利用 エ)2001年度中に、インターネット上で取引されるコンピュータ・ソフトウェアの保護の明確化等インターネット上での知的財産保護についての検討を行い、特許法の見直しなど、所要の制度整備に取り組む。 |
(2)産業構造改革・雇用対策本部 中間とりまとめ
(平成13年6月26日 産業構造改革・雇用対策本部決定)
1.新市場、新産業の育成による雇用創出
- 戦略基盤・融合技術分野への重点投入(産学官総力戦)
- 知的財産権保護政策の強化等
- インターネット上でのコンピュータ・ソフトウェアや商標の保護の明確化等を図る観点から、次期通常国会に特許法・商標法等の見直しを行う法案を提出すべく、検討を進める。(経済産業省)
1.ソフトウェア等情報財の特許保護強化とネットワーク取引の促進
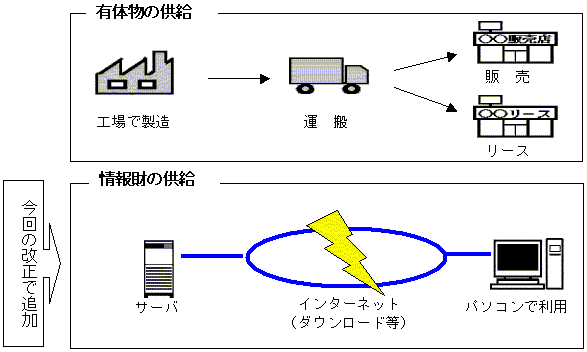
2.特許法の間接侵害規定の拡充
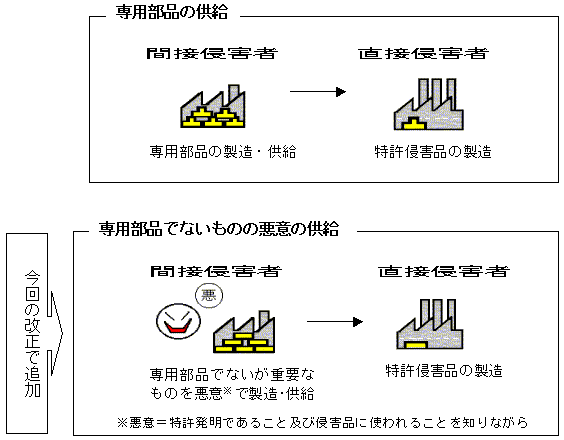
3.ネットビジネスで使用される商標の信用保護強化
(1)商品商標の使用行為様態として、インターネット送信を追加
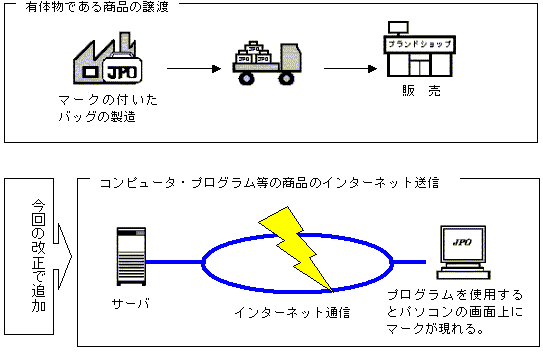
(2)サービスマーク(役務商標)の使用行為様態として、画面上に表示される場合を追加
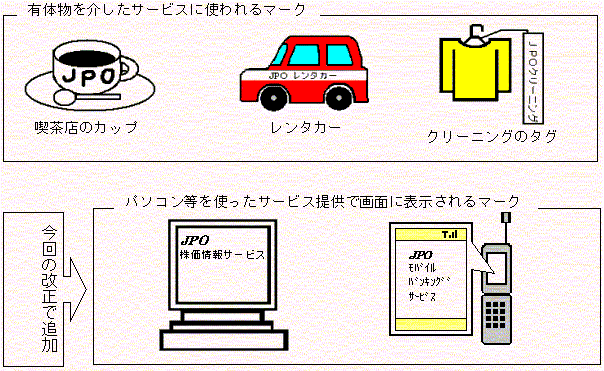
[特許法等の一部を改正する法律について(平成14年4月17日掲載)]からリンク
[更新日 2002年8月7日]
|
お問い合わせ |
|
特許庁総務部総務課制度改正審議室 TEL:03-3581-1101 内線2118 |