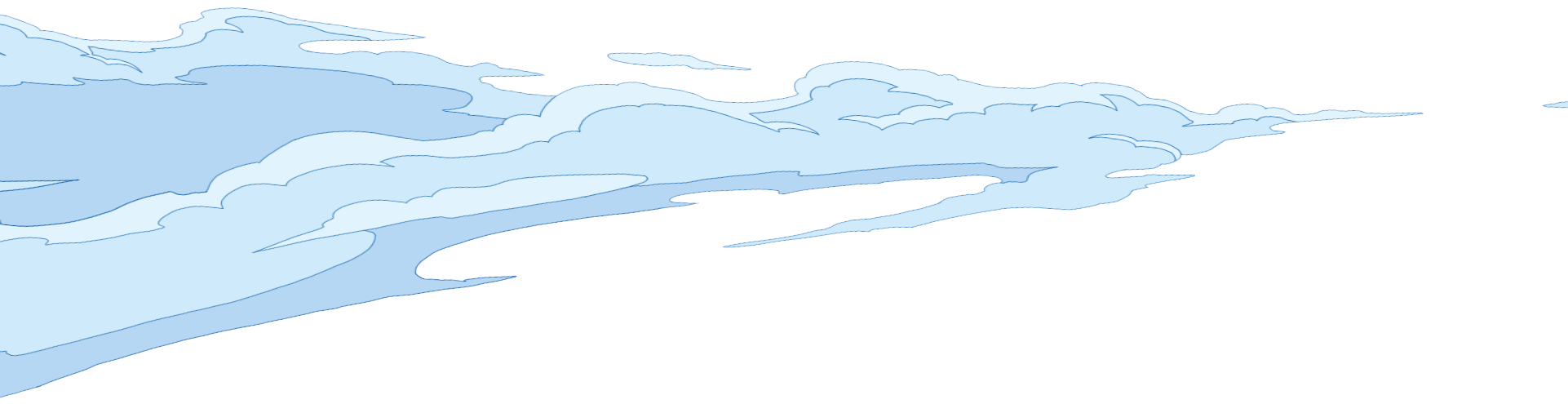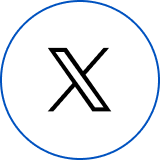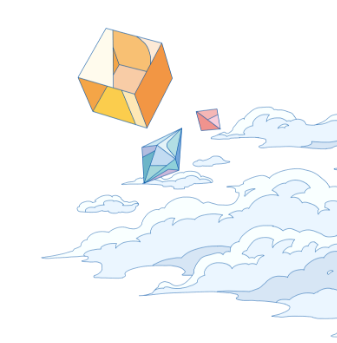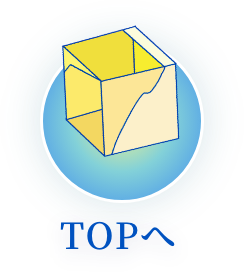ここから本文です。

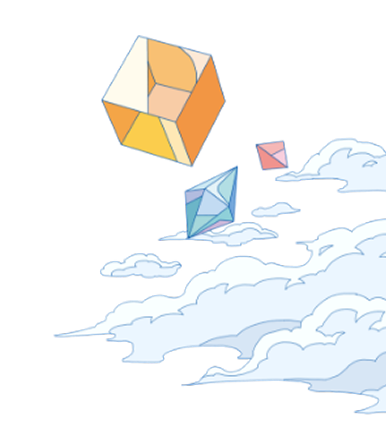

-

甲子化学工業株式会社
知財で伝える、環境と安全への想い
貝殻がやっかいな廃棄物に
日本最北端の村、北海道・猿払村(さるふつむら)。人口約2,500人のこの小さな村は、日本一のホタテの漁獲量でも知られています。
ただ、日本一ゆえの深刻な悩みも抱えています。それが、貝殻の問題。
ホタテを加工する際に水産系廃棄物として発生する貝殻は、なんと年間約4万トンにも達します。
廃棄された貝殻の環境への影響や堆積場所の確保など、地元は長年にわたって頭を悩ませてきました。
「猿払の宝」と大切にされているホタテは、同時に厄介者の廃棄物を生み出す存在でもあったのです。
再利用で資源に
そんな猿払村の現状を目にして、行動を起こした人がいました。大阪の町工場で働く南原徹也さんです。
ホタテの貝殻が堆積場に山のように積まれている様子をたまたま知った南原さんの頭にひらめいたのは、ホタテの貝殻を資源として活用できないかというアイデアでした。
南原さんが働いているのは、1969年創業のプラスチックメーカー。現、経営者である父の跡継ぎである南原さんは、SDGsの流れの中で新たなエコプラスチックの開発に挑戦しており、自社の加工技術を使えばホタテの貝殻を原料として再利用できないかと考えました。
南原さんはすぐに行動しました。猿払村に連絡を取り、貝殻が積み上げられている水産加工場を訪ねました。
野ざらしのままなら廃棄物。再利用すれば貴重な資源。
南原さんは約300キロもの貝殻を大阪に持ち帰って実験に取りかかりました。
約36%もCO2を削減
大阪の工場に帰った南原さんは、貝殻を砕いて、様々な種類のプラスチックと混ぜ合わせる実験を進めました。
その結果、誕生したのが廃棄ホタテ貝殻とプラスチックを再利用した新素材です。
一方で、この新素材を活かして何が生み出せるか、用途も検討。
「外敵から身を守るのが貝殻だから、人の安全を守る防災用品はどうだろう」
頭に浮かんだのは、ヘルメットでした。
せっかくなら当たり前のデザインのヘルメットでは面白くない。南原さんはホタテ貝の形から着想を得て、表面に波型の加工を施すことに。これで貝殻から生まれたヘルメットということが一目でわかるようになりました。こうして誕生したのが防災ヘルメット“HOTAMET”(ホタメット)です。新品のプラスチックを使用するより最大で約36%のCO2削減につながる、環境配慮型のヘルメットでもあります。
“HOTAMET”(ホタメット)は万博の公式ヘルメットとして採用されるとともに、防災用品としての備蓄や、一般向け販売、ふるさと納税返礼品としての導入などを通じて全国へ展開中です。
知財を取得し、全国へ展開
廃棄されるホタテの貝殻に付加価値を持たせて再利用する「アップサイクル」の取り組みによって生まれた新素材は“SHELLTEC”(シェルテック)という商標権を取得。また、波型の加工が目を引く“HOTAMET”(ホタメット)は、デザイン保護の意匠権を取得しました。
南原さんはこれらの権利を「想いを同じくする人にライセンスしていきたい」としています。
廃棄物が新素材として甦り、人々の安全と環境を守っていく。知財は、そんな取り組みをサポートしています。
甲子化学工業株式会社
1969年創業のプラスチック製品メーカー。大阪市に本社を構え、生活雑貨や医療・産業向け製品を製造。環境負荷を減らす循環型素材の開発にも注力。さらに、パートナー企業との協業を通じた新製品の開発や、廃棄貝殻のさらなる活用にも取り組み、持続可能なものづくりを推進している。
【知的財産活用】
商標権と意匠権を取得。意匠権は特許に比べて容易に取得可能なことが多い一方で、模倣品から自社製品をしっかり保護できる。
【関西知財活用支援プラットフォーム】
甲子化学工業株式会社は、近畿経済産業局・日本弁理士会関西会・日本弁理士会北陸会及びINPIT-KANSAIの協力の下に実施する関西知財活用支援プラットフォームで支援した企業です。関西知財活用支援プラットフォームは、2025年大阪・関西万博までに、知財を稼ぐ力にして経営を行う企業を関西で多く創出することを目的として、3つの機関の強み・施策をミックスして、中小・中堅企業における知財面の課題解決や事業展開に合致した知財活用の支援を実施する事業です。
展示紹介ムービーはこちら >
別ページでYouTubeが開きます。(外部サイトへリンク)