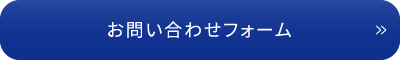ここから本文です。
知財仲裁ポータルサイト
知財紛争を解決する手段には、裁判と、裁判外紛争解決手続(ADR)があります。
ここでは、ADRの1つである仲裁による知財紛争解決について紹介します。

制度情報
裁判外紛争解決手続(ADR)とは
裁判以外の方法で法的な紛争を解決する手続一般を総称する言葉で、英語では「Alternative Dispute Resolution」(「裁判に代替する紛争解決手段」)といい、頭文字をとって「ADR(エー・ディー・アール)」と呼ばれることがあります。「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」では、「訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続」とされています。
ADRには、仲裁や調停など、様々なものがあります。
「仲裁」は、当事者の合意(仲裁合意)に基づいて、仲裁人で構成される仲裁廷が事案の内容を調べた上で判断(仲裁判断)を示し、当事者がこれに従うべきこととなる手続です。「調停」は、当事者の間を調停人が中立的な第三者として仲介し、紛争の解決についての合意ができるように、話し合いや交渉を促進したり、利害を調整したりする手続です。
知財仲裁について
知財のような専門性が高い分野においては、知財に関する専門的知見を有する者を仲裁人として選任することで紛争を効率的に解決できる場合があります。
また、例えば特許技術を使った製品が世界的に流通しているような場合、特許紛争が世界各国で同時に発生することがあります。仲裁には、外国の仲裁判断を国内で強制執行することを可能とする「外国仲裁判断の承認及び執行に関する条約」(ニューヨーク条約)があり、現在150以上の国が加盟しているため、仲裁によって、ニューヨーク条約加盟国で起きている紛争を効率的に解決できる場合があります。
最近の議論
平成30年2月に、特許制度小委員会でとりまとめられた報告書「第四次産業革命等への対応のための知的財産制度の見直しについて」において、「多数の特許権が対象となる標準必須特許を巡る紛争の早期解決に向けては、調停や仲裁等のADRの利用を促進することが有効である」、「標準必須特許をはじめとした知的財産関連の紛争においても、国際仲裁の利用促進が図られることが期待される」とされており、特許庁としても国際仲裁を始めとするADRについての情報発信に努めています。