ここから本文です。
平成11年改正意匠法 意匠審査の運用基準
平成11年12月
特許庁
まえがき
この「平成11年改正意匠法意匠審査の運用基準」は、平成11年の改正意匠法の施行日である平成12年1月1日を控えて、意匠審査実務が行われる前に、意匠審査実務に係る各種の判断基準、取扱い等を定めたものである。
本運用基準を策定・公表することにより、改正法下において、意匠登録出願人、代理人にあっては新たな制度を有効に活用できるように、意匠審査官・審判官、事務官にあっては新たな制度に係る円滑な審査・審判事務の遂行及び業務の運用ができるように期待するものである。
目次
I.意3条1項(出願前公衆利用可能意匠の保護除外)
1.改正の趣旨
2.意3条1項2号の規定に該当する意匠
3.「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」について
- 3.1「回線」について
- 3.2「公衆に利用可能」について
- 3.3「公衆に利用可能となった意匠」について
4.この運用基準が適用される意匠登録出願
II.意4条(出願前公開意匠の新規性・創作容易性判断の適用除外)
1.改正の趣旨
- 1.1 旧法4条の概要
- 1.2 旧法下での問題点
- 1.3 改正理由
2.意4条1項及び2項の規定の概要
3.意4条1項の規定について
- 3.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図
- 3.2 意4条1項の規定の適用を受けるための要件
- 3.3 意4条1項の規定の適用を受けるための手続
4.意4条2項の規定について
- 4.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図
- 4.2 意4条2項の規定の適用を受けるための要件
- 4.3 意4条2項の規定の適用を受けるための手続
5.この運用基準が適用される意匠登録出願
I.意3条1項(出願前公衆利用可能意匠の保護除外)
改正条文
(意匠登録の要件)
第3条 工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。
- 一 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- 二 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた意匠
- 三 前二号に掲げる意匠に類似する意匠
(2項省略)
1.改正の趣旨
近年、インターネット等(注1)で開示されているデザイン情報は、雑誌やカタログ等の刊行物により開示されるデザイン情報と同等の内容を有し、その情報伝達の迅速性・安価性等の利便性から、企業側も製品発表を刊行物や展示会だけでなく、インターネット等を通じた製品情報の発表を行うケースも増えてきている。その発表は、場合によっては、インターネット等を通じてのみ行われたり、他の発表に先行して行われるケースも見受けられる。
しかし、インターネット等を通じて開示される意匠は、平成11年改正前の意匠法(以下、「旧法」という。)においては、一般的な公知意匠として取扱うことにより、意3条1項1号又は同条同項3号によって新規性喪失事由となり得たが、公然知られた意匠であることを立証することが難しいことから、旧法においては、インターネット等で開示されたことをもって新規性喪失事由とすることは困難であった。
そこで、インターネット等で開示された意匠について、頒布された刊行物に記載された意匠と同様、新規性喪失事由となるように旧法3条1項2号の改正を行ったものである。
(注1)「インターネット等」とは、電気通信回線を通じてデザイン情報を提供するインターネット、商用データベース、メーリングリスト(インターネット上で特定のメンバーに一斉に同報電子メールを送るシステム)等すべてを指す。
2.意3条1項2号の規定に該当する意匠
意3条1項2号の規定に該当する意匠とは、
- (1)意匠登録出願前に日本国内又は外国において頒布された刊行物に記載された意匠
又は、 - (2)意匠登録出願前に日本国内又は外国において電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
をいう。
3.「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」について
- 3.1「回線」について
往復の通信路で構成された、双方向に通信可能な伝送路を意味し、一方向にしか情報を送信できない放送(双方向からの通信を伝送するケーブルテレビ等は除く。)は、双方向に通信可能な伝送路ではないので、同条同項に規定する回線とはいえない。 - 3.2「公衆に利用可能」について
社会一般の不特定の者が見得るような状態に置かれていることをさし、現実に社会一般の不特定の者が見たという事実は必要としない。 - 3.3「公衆に利用可能となった意匠」について
当該意匠登録出願前に、電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった事実が存在すれば足りる。
4.この運用基準が適用される意匠登録出願
平成12年1月1日以降にした意匠登録出願について適用する。
II.意4条(出願前公開意匠の新規性・創作容易性判断の適用除外)
改正条文
(意匠の新規性の喪失の例外)
第4条 意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠は、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項第一号又は第二号に該当するに至らなかつたものとみなす。
2 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠も、その該当するに至つた日から六月以内にその者がした意匠登録出願に係る意匠についての同条第一項及び第二項の規定の適用については、前項と同様とする。
3 (文頭削除)前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、第三条第一項第一号又は第二号に該当するに至つた意匠が前項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面を意匠登録出願の日から十四日以内に特許庁長官に提出しなければならない。
1.改正の趣旨
- 1.1 旧法4条の概要
旧法においては、新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができる場合は、旧法4条1項及び2項の規定により、 意匠登録を受ける権利を有する者(意匠の創作者、又はその承継人)の意に反して、例えば、その者が知らない内に創作した意匠が公然知られたり刊行物に掲載されたときに、その公開の事実の日から6か月以内に当該公開された意匠を意匠登録出願したとき、又は、
意匠登録を受ける権利を有する者(意匠の創作者、又はその承継人)の意に反して、例えば、その者が知らない内に創作した意匠が公然知られたり刊行物に掲載されたときに、その公開の事実の日から6か月以内に当該公開された意匠を意匠登録出願したとき、又は、 意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、例えば、創作した意匠を展示行為などによって本人の意思で公表したり刊行物に掲載したときに、その公開の事実の日から6か月以内に当該公開された意匠を意匠登録出願し、意4条2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に提出し、その公開の事実を証明する書面を出願の日から14日以内に提出したときに限られた。
意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、例えば、創作した意匠を展示行為などによって本人の意思で公表したり刊行物に掲載したときに、その公開の事実の日から6か月以内に当該公開された意匠を意匠登録出願し、意4条2項の規定の適用を受けようとする旨を記載した書面を出願と同時に提出し、その公開の事実を証明する書面を出願の日から14日以内に提出したときに限られた。
- 1.2 旧法下での問題点
- (1) 意匠登録出願前の意匠の実施の状況をみると、その意匠の売れ行きを打診するために当該意匠の見本の頒布、展示等を行う場合には、同時に数種のバリエーションの意匠についても、その見本の頒布、展示等がよく行われているところであり、その場合には、それらの意匠が互いに類似する意匠であることも少なくない。
このような状況において、例えば、公開された意匠のうち一の意匠について意匠登録出願をする場合には、当該公開された意匠について新規性の喪失の例外の規定の適用を受けることができるが、旧法4条2項は、同法3条1項3号に言及していないことから、同時に公開された他の類似する意匠についてはその適用を受けることができなかった。 - (2) 産業界の商品開発の実態をみると、同時期に発売する商品については、数種類の類似する意匠を同時に創作するケースが多く見られるが、それらの公開時期は必ずしも同時でない場合もある。このように、当該意匠登録出願に係る意匠が初めて公開された時から出願されるまでの間に、その意匠に類似する意匠を当該意匠登録出願の出願人自らが公開した場合であっても、当該意匠登録出願の意匠は、初めて公開されたときから出願されるまでの間に公開された意匠によって旧法3条1項3号の規定により拒絶となった。
- (3) 意3条2項では、例えば、創作者が自ら創作した複数の意匠を、公然知られた状態にしたとき、又は頒布された刊行物に記載したとき、その後、それらの意匠を当業者にとってありふれた手法により寄せ集めた意匠として意匠登録出願をすると、当該意匠登録出願の意匠は、意3条2項の規定により拒絶(注2)となった。
(注2) 意3条2項は、「…公然知られた形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合に基づいて…」と規定されているが、容易な意匠の創作とは、公然知られた「意匠」そのものをそのまま借用せずに当該「意匠」から「形状、模様若しくは色彩又はそれらの結合」を抽出したものを再度「意匠」の形状、模様若しくは色彩またはこれらの結合に再構成する行為も含まれるものである。したがって、創作容易性を判断する資料としては、「形状、模様若しくは色彩又はそれらの結合」に加えて運用上は「意匠」も含め、公開された意匠に基づき容易に創作できた意匠についても同法同条同項の規定の適用が有りうる。
(平成10年改正意匠法意匠審査の運用基準第1部Ⅰ.意3条2項2.4「判断の基礎となる資料」参照)
- (1) 意匠登録出願前の意匠の実施の状況をみると、その意匠の売れ行きを打診するために当該意匠の見本の頒布、展示等を行う場合には、同時に数種のバリエーションの意匠についても、その見本の頒布、展示等がよく行われているところであり、その場合には、それらの意匠が互いに類似する意匠であることも少なくない。
- 1.3 改正理由
上記のような状況及び意匠法の趣旨を勘案すると、意匠登録を受ける権利を有する者に対するいわゆる救済規定である旧法4条の規定では、第三者への影響を考慮したとしても不十分なものといわざるを得ない。
そこで、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して又は意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して意3条1項1号又は同条同項2号に該当するに至った意匠によって、その者がした後日の意匠登録出願の意匠が、意3条1項各号及び同条2項の規定により拒絶されないように旧法4条の規定を改めることとした。
2.意4条1項及び2項の規定の概要
創作された意匠が、その公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」の意に反して(意4条1項)、又は、当該「意匠登録を受ける権利を有する者」の行為に起因して(意4条2項)、「日本国内又は外国において公然知られた意匠(意3条1項1号に規定する意匠)」又は、「日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠(意3条1項2号に規定する意匠。前項の公然知られた意匠と合わせて、以下「公開意匠」という。)」に該当するに至ったときは、その公開意匠が最初に公開された日から6か月以内に当該公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」が意匠登録出願し、所定の要件を満たした場合に限り、前記公開意匠は、その意匠登録出願前に「日本国内又は外国において公然知られた意匠」又は、「日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠」ではないとみなし、当該意匠登録出願の意匠に限って同法3条1項各号及び同条2項の規定に該当するか否かの判断の対象から除外する、という規定である。
なお、公開意匠と当該意匠登録出願の意匠の関係については、旧法4条においては、両意匠が同一又は同一性を有していることが要件となっていたが、改正法4条においては、両意匠の関係について何ら規定されていないため、両意匠が同一、類似又は非類似であるか否か等、両意匠の関係が如何なるものかに関わらず、公開意匠及び当該意匠登録出願が所定の要件を満たせば、その公開意匠について改正法4条1項又は2項の規定の適用が受けられることとなる。
3.意4条1項の規定について
3.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図
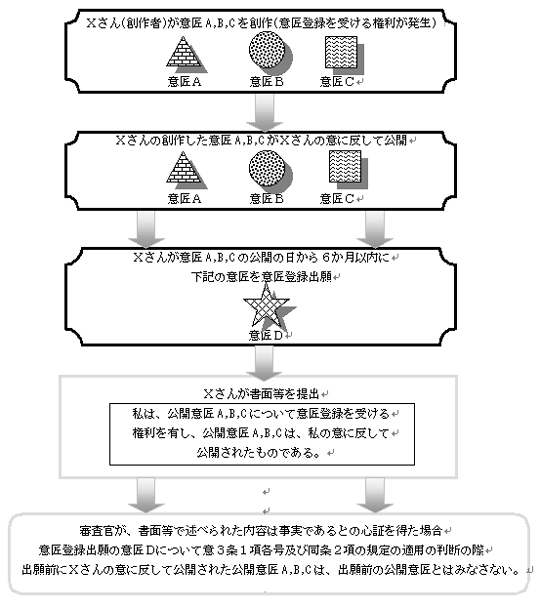
3.2 意4条1項の規定の適用を受けるための要件
下記の要件が満たされた場合に意4条1項の規定が適用される。
- 3.2.1 創作された意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して、下記のいずれかの意匠に該当するに至ったものであること
- (1) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- (2) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
この要件を満たすためには、下記の事項が書面により明示されるとともに証明される必要がある。
- 3.2.1.1 公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」
「公開意匠が、当該公開意匠についての『意匠登録を受ける権利を有する者』の意に反して公開されたこと」が要件の一部であることから、公開意匠についての公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」が明示されると共に証明される必要がある。
一般に、公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」は公開意匠の創作者であるが、公開意匠の公開前に、公開意匠の創作者が意匠登録を受ける権利を第三者へ承継して公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」が創作者と相違する場合には、その事実が明示されると共に証明される必要がある。 - 3.2.1.2 公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」の意に反して公開された事実
公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」の意に反して公開される場合とは、例えば、創作者の創作した意匠が窃取盗用によって第三者に公開された場合等(参考判決参照)が考えられる。
いずれにしても、どのような経過を経て、公開意匠が公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」の意に反して公開されたかという事実が明示されると共に証明される必要がある。 - 3.2.2 公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」が、意匠登録出願をしていること
意4条1項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願にあっては、「その者がした意匠登録出願」であることが要件の一部であることから、3.2.1.1において証明された、公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」と当該意匠登録出願の願書に記載された出願人とが一致していなければならない。
公開時における公開意匠についての「意匠登録を受ける権利を有する者」と当該意匠登録出願の願書に記載された出願人とが相違する場合には、公開意匠の公開後に、当該公開意匠についての意匠登録を受ける権利が当該出願人に承継されている事実が明示されると共に証明される必要がある。
- 3.2.3 当該意匠登録出願が、公開意匠が最初に公開された日から6か月以内に出願されていること
この要件を満たすためには、当該公開意匠が最初に公開された年月日について、まず明示されると共に証明される必要があり、その日から6か月以内に意匠登録出願されていなければならない。
3.3 意4条1項の規定の適用を受けるための手続
意4条1項の規定の適用を受けるための手続(同条同項の規定の適用を受けたい旨を記載した書面の提出あるいは願書面への適用を受けたい旨の記載、意匠登録を受ける権利を有する者の意に反して公開された事実の証明書の提出等)は何ら法律に規定されていない。
したがって、当該意匠登録出願の出願人は、「当該意匠登録出願後に、当該意匠登録出願前の公開意匠が『意匠登録を受ける権利を有する者』の意に反して公開された事実が判明した時」、例えば、「当該意匠登録出願の意匠が同法3条1項各号のいずれかの規定に該当する、又は同法3条2項の規定に該当する旨の拒絶理由通知書中にその理由として記載された公開意匠が、『意匠登録を受ける権利を有する者』の意に反して公開された事実が判明した時」に、書面により前記3.2の要件を満たす事実を明示すると共に証明すればよい。
なお、出願人は、出願前に前記3.2の要件を満たす公開意匠の存在が判明している場合には、出願と同時にその事実を証明する書面を提出してもよい。
(参考判決)旧法4条1項の規定の適用が認められた判決例
昭和53年(行ケ)第91号「灰皿」
理由(前文省略)
成立に争いのない甲3号証、第4号証、乙2号証、証人Hの証言及び原告本人尋問の結果に、弁論の全趣旨を合わせて考えると、次の事実が認められ、この認定に反する証拠はない。
「原告は、灰皿、ライター、靴べら等の日常雑貨品の製造販売を業とするT社の代表取締役であり、これまで自己が開発した意匠等に係るこの種雑貨品の製造販売をT社にさせていたものであるが、昭和50年5月ころ、ドラム缶を模した灰皿を考案して、その意匠登録出願の手続をN弁理士に委任する一方、その試作品を、かねて取引のあったN社の代表取締役Kに渡して、この種灰皿を製造販売したい意向を伝えたが、その際、T社において販売体制が整うのに少なくとも数ヶ月を要する見込みであったので、このような条件が整った後に改めて広告や販売方法に関する具体的な打ち合わせを行うこととし、それまでは広告や見本の対外的な呈示などはしないよう要請し、同人もこれを了承した。上記Kは、そのころ、N社の従業員Yに上記試作品を渡して広告の立案を指示したので、同人は、その原稿を作成したが、同年6月初めころからN社には出勤しないようになり、そのまま同社を退社してしまった。同社における同人の仕事を受け継いだHは、同年6月20日ころ、雑誌「○○○○」を発行している株式会社B社のIが同誌に掲載する広告記事がないかどうかを問い合わせに来訪した際に、原告とKとの間に前記のような合意がされていた事情を知らないまま、Yの作成に係る前記原稿を試作品と共に上記Iに渡し、その結果、雑誌「○○○○」の同年7月号に本件灰皿に係る意匠の広告が掲載されるに至った。」
上記認定の事実からすれば、引用意匠に係る同誌の灰皿の写真は出願人たる原告の意に反して刊行物に記載され、・・・(以下省略)。
4.意4条2項の規定について
4.1 同条同項の規定の適用の一般的な模式図
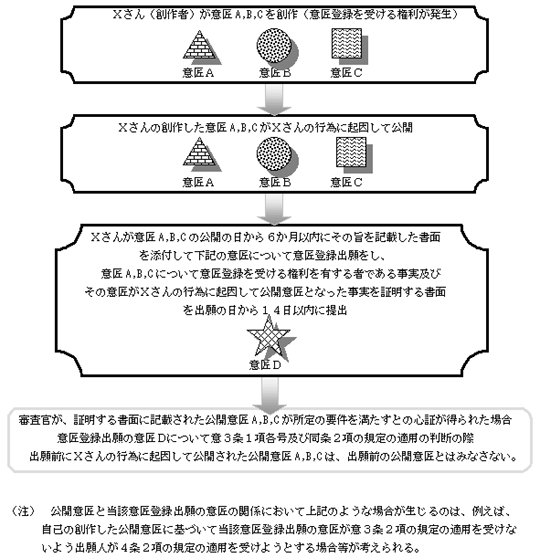
4.2 意4条2項の規定の適用を受けるための要件
意匠登録出願の出願の日から14日以内に提出された「証明する書面」に記載された意匠が、下記の要件を満たす場合に意4条2項の規定が適用される。
- 4.2.1 創作された意匠が、意匠登録を受ける権利を有する者の行為に起因して、下記のいずれかの意匠に該当するに至ったものであること
- (1) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において公然知られた意匠
- (2) 意匠登録出願前に日本国内又は外国において、頒布された刊行物に記載された意匠又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった意匠
この要件を満たすためには、下記の事項が「証明する書面」により明示されるとともに証明される必要がある。
- 4.2.1.1 「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」「公開意匠が、当該公開意匠についての『意匠登録を受ける権利を有する者』の行為に起因して公開されたこと」が要件の一部であることから、公開意匠についての公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」が明示されると共に証明される必要がある。
一般に、公開意匠についての公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」は公開意匠の創作者であるが、公開意匠の公開前に、公開意匠の創作者が意匠登録を受ける権利を第三者へ承継して公開意匠についての公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」が創作者と相違する場合には、その事実が明示されると共に証明される必要がある。 - 4.2.1.2 「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」の行為に起因して、当該公開意匠が公開された事実
「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」の行為に起因して、当該公開意匠が意3条1項1号又は2号の意匠に該当するに至った事実が明示されると共に証明される必要がある。 - 4.2.2 「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」が、意匠登録出願をしていること
意4条2項の規定の適用を受けようとする意匠登録出願にあっては、「その者がした意匠登録出願」であることが要件の一であることから、4.2.1.1において証明された、「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」と当該意匠登録出願の願書に記載された出願人とが一致していなければならない。
「証明する書面」に記載された公開意匠の公開時における「意匠登録を受ける権利を有する者」と当該意匠登録出願の願書に記載された出願人とが相違する場合には、公開意匠の公開後に、当該公開意匠についての意匠登録を受ける権利が当該出願人に承継されている事実が明示されると共に証明される必要がある。 - 4.2.3 当該意匠登録出願が、「証明する書面」に記載された意匠が最初に公開された日から6か月以内に出願されていること
この要件を満たすためには、当該公開意匠が最初に公開された年月日について、まず明示されると共に証明される必要があり、その日から6か月以内に意匠登録出願されていなければならない。
4.3 意4条2項の規定の適用を受けるための手続
- (1) その旨を記載した書面が意匠登録出願と同時に特許庁長官に提出されているか(意4条3項)、あるいは願書にその旨が記載されていなければならない(意匠法施行規則28条2項で準用する特許法施行規則27条の4)。
- (2) その意匠登録出願の日から14日以内に、意3条1項1号又は2号に該当するに至った意匠が意4条2項の規定の適用を受けることができる意匠であることを証明する書面が提出されていなければならない。
- (3) 「証明する書面」の提出は、意匠法施行規則1条で定める様式第一によりしなければならない。
5.この運用基準が適用される意匠登録出願
平成12年1月1日以降にした意匠登録出願について適用する。
[更新日 2005年10月13日]
|
お問い合わせ |
|
特許庁審査第一部意匠課意匠審査基準室 電話:03-3581-1101 内線2910 |