ホーム> 制度・手続> 法令・施策> 法令・基準> 基準・便覧・ガイドライン> 商標> 指定商品の書換制度について> 書換手続に関するQ&A
ここから本文です。
書換手続に関するQ&A
Q1.書換とは何ですか
A.「書換」とは、旧商品区分のもとで登録された商標権の指定商品を、国際分類に基づく現行の商品区分及び指定商品に書き換えることをいいます。
旧商品区分とは、平成4年3月31日までにされた商標登録出願に適用される商品区分をいいます。
具体的には、明治32年法、明治42年法、大正10年法及び昭和34年法による各商品区分のことで4種類のものがあります。
なお、現行商品区分とは、平成4年4月1日以降の出願に適用される商品区分のことです。
Q2.なぜ、書換が必要なのですか
A.現行商品区分と旧商品区分とでは、その区分の構成や商品の表示が相違するため、調査が煩雑であることや権利範囲が不明確である等の問題が生じていました。
そこで、今回、旧商品区分の商標権の指定商品を現行商品区分のものに書換えることにより、問題の解消を図ることにしました。
Q3.書換の対象範囲は
A.書換の対象となるのは、平成4年3月31日までの出願に係る商標権です。
具体的には、明治32・42年法、大正10年法及び昭和34年法の各法区分に基づき出願された商標権が該当します。
なお、上記の各法区分に基づき出願された商標権とは、以下の期間に出願されたものをいいます。
- 1)明治32・42年法・・・・・・大正11年1月10日までに出願されたもの
- 2)大正10年法・・・・・・・・・大正11年1月11日から昭和35年3月31日までに出願されたもの
- 3)昭和34年法・・・・・・・・・昭和35年4月1日から平成4年3月31日までに出願されたもの
Q4.必ず書換申請をしなければなりませんか
A.平成4年3月31日以前に出願した商標権を所有する商標権者は、書換をしなければなりません。
なお、書換をしなくても、「商標権存続期間更新登録申請書」を提出して更新登録されると、10年間は商標権を維持することができますが、次回の更新はできません。
(*書換の対象となっている商標権が、すでに不必要なものとなっている場合は、更新申請・書換申請のいずれの手続きも必要ありません。)
Q5.書換申請の時期はいつですか
A.商標権者は受付開始日から起算して6月に達する日以降、最初に到来する商標権の満了日の前6月から満了日後1年の間に書換申請が必要です。(これらの期間を図示すると次のとおりです。)
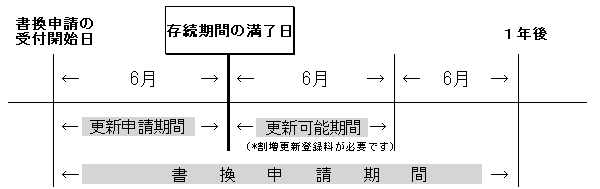
なお、書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換申請の受付開始日は、特許庁長官が指定することとなっていますが、平成11年10月13日付けで昭和34年法に基づく商標権等の書換申請の受付開始日が指定されたことにより、以下のとおり、各法区分の書換申請の受付開始日は、全て指定されました。
- 明治32年法及び明治42年法に基づく商標権→受付開始日は平成10年4月1日
- 大正10年法に基づく商標権→受付開始日は平成11年4月1日
- 昭和34年法に基づく商標権及び防護標章登録に基づく権利→受付開始日は平成12年4月1日
書換申請の受付開始時期については、以下の図を参照してください。
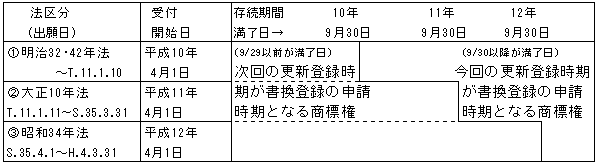
Q6.書換申請の時期には何か通知があるのですか
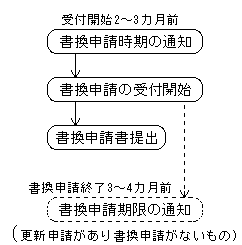
A.書換申請時期が近づきますと、全ての商標権者(又は代理人)に対し「書換申請時期の通知」(葉書)が送付されますからこの通知を待って書換申請期間内に手続を行うことができます。〔右図参照〕(但し、権利者の登録原簿上の住所と現住所が相違しますと葉書は配達されませんので注意が必要です。)
また、更新申請時期と書換申請時期とは、ほぼ同じ時期ですので、同時に手続をすると便利です。
(注)書換の申請漏れを防ぐため、書換申請開始日の2カ月から3カ月前に、商標権者に対し書換申請の開始時期が近づいた旨の通知をします。
また、更新申請があっても書換申請がないものについては、書換申請期間終了日の3カ月から4カ月前に申請期間終了の期限が迫っている旨を通知することとしています。
Q7.書換申請の手続はどうするのですか
A.「書換登録申請書」を作成して、特許庁にパソコン電子出願、郵送又は持参により提出(申請)します(なお、書面による申請書を郵送又は持参により提出する場合は、電子化手数料(1,200円+700円×書面の枚数)が必要となります。)。
この申請書の様式は、商標法施行規則(様式第21)で定められています。
(申請書の詳細については最後に付けた「書換申請書の様式」を参照のこと)
なお、書換申請時期は商標権存続期間の更新登録申請時期とほぼ同じであることから、書換の手続は更新登録申請の手続と同時にすると便利です。書換申請があると特許庁の審査官により審査が行われます。
(手続の詳細については最後に付けた「書換手続フロー」を参照のこと)
Q8.どのように書換えるのかのガイドブック等はありますか
A.旧商品区分の商品を、国際分類第10版の商品へ書き換える書換のガイドラインは、発行していません。
指定商品並びに商品の区分等について、御不明な点があれば、<この記事に関する問い合わせ先(特許庁審査業務部商標課商標国際分類管理室)>までお問い合わせください。
Q9.書換のための手数料や登録料は必要ですか
A.書換申請の手数料や書換登録料は無料です。ただし、書換に係る審判請求(書換申請が拒絶された場合の不服審判、他人が行った書換登録についての無効審判)については手数料が必要です。
なお、書換が登録された後の次の更新の際には、書換登録後の商品区分数に応じた更新登録料を納付しなければなりません。例えば、3区分となった場合、その区分数(3区分)の料金が必要です。
( 書換登録申請書の様式 )※申請書用紙はA4サイズで作成してください。
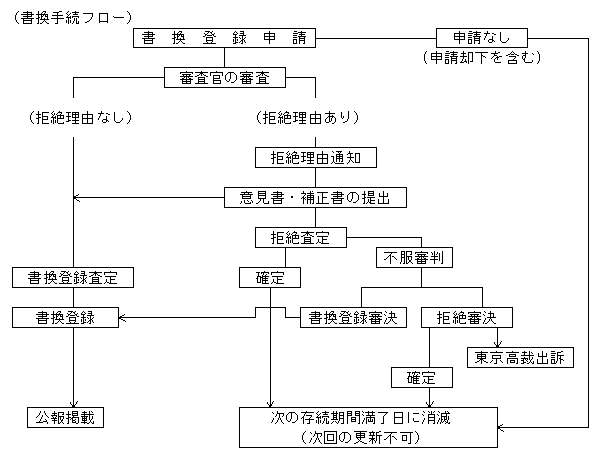
[更新日 2012年7月31日]