ここから本文です。

Vol.47
広報誌「とっきょ」2021年2月5日発行
自動運転の世界を支える技術開発と知財の戦略!
ー「競争」だけでなく「協創」が求められる時代に突入している
「現在、業界全体で取り組んでいる『自動運転技術』を実用可能なものへと進めるためには、複合的な技術が必要です。 例えば、自動車の位置を把握するためのGPS機能や、障害物との距離を測るセンサー機能、それらデータを解析する処理機能、さらに処理されたデータに基づいて自動車を正しく動かさなければなりません。
もちろんデータのやりとりを行う通信技術だけでなく、そのデータを扱うための半導体や、セキュリティ、レーダー系の技術も重要なポイントとなります。基本的に、自社で開発を進めてきたのですが、前述の理由から他業種との共同開発という選択肢が生まれました。これまで『開発』というと、必ずと言っていいほど『競争』というキーワードがセットとなっていました。しかし、近年の弊社で『開発』といった場合、『協創』というキーワードがついてくるのです。
『協創』という言葉は、弊社がどこかと共同で開発をすることだけを指すのではなく、業界として先を見通した開発を行えるように考 えた戦略から生まれた概念です。」
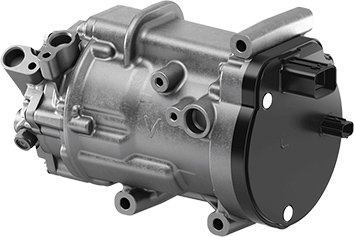
ー 知財に対する取り組み方と自動運転技術の未来について
「元々、弊社では他社の見本となるような知財活動を目指して、取組を進めてきました。
知財は会社のビジネスと連携して初めて価値が高まります。そのような考え方が根付いたのは、2007年頃。それまでは、どちらかと言えば『件数』が重視されていましたが、あるとき経営陣から『特許は価値を見せるべき』との声があがりました。その声に応えるために、他部門とも頻繁に議論するようになり、それによって、他部門との距離が縮まり『各事業と連携した特許の取得を進めて行きましょう』という流れができてきたと思います。
事業部単位で特許推進会議を構築し、各事業部の製品に応じて知財の課題とターゲットを議論する場を設けました。その結果、各事業部が知財を事業の一つとして考えるようになったのです。
2010年頃からは、パテントトロールの係争に巻き込まれることが多くなってきたこともあり、知財が経営マターであるとの認識が経営層にも広まっていきました。知財部自身も、その都度活動のテーマを設定し、事業部や技術部にコミットしながら、特許情報などを通じて強みや弱みを提示するなど、常に矢面に立って対応してきました。そのことが、自らを成長させることにつながってきたと考えています。
先ほども申し上げましたが、自動運転の技術が進むにつれ、ますます他社との協創が必要となるでしょう。
全てを自前で開発しようと思えば、競合他社に遅れを取ってしまいます。他社と協創することにより、最先端の技術を他の業種からうまく導入していくことが重要なポイントとなるでしょう。
協創の際には、まずは自社がしっかりとした技術を持っていることが重要です。自社の強みをしっかりと意識しつつ、将来の協創先を想定した上で、必要な領域での権利化を進める必要もあります。また、協創先の検討の際には、知財情報などを用いて分析も行うため、知財部の役割はますます重要になっていくと考えています。
これからは知財についても、多角的な考え方が求められる時代です。常に経営層、事業部や技術部と強く連携し、『伸びゆく市場、変わりゆく市場に対し、顧客の期待を先読みし、最適パートナーとともに事業開拓を推進する』という方針のもと、適切な対応を図っていきます。」
世界のクルマ産業を牽引するデンソーが、自動運転の技術により、業界をさらに加速させる未来は、そう遠からず訪れるのかもしれません。
