ここから本文です。

Vol.63
広報誌「とっきょ」2024年12月17日発行号
特集1
持続可能な食料生産システムへの道
食の社会課題に知財で挑む!

増え続ける人口と気候変動の激化によって、世界の食料生産システムが大きな曲がり角に差し掛かっている。タンパク質不足や海の生態系変化といった「食」の社会課題の解消のために、特許技術とそれを活用した枠組の構築に取り組む先進的な事例を紹介する。
世界の爆発的な人口増加や気候変動が従来の食料供給を脅やかす
世界の「食料問題」は多岐にわたるが、その中でも特に影響範囲が広く、かつ喫緊の課題として、大きく三点が挙げられる(下図)。
食物に含まれる三大栄養素(炭水化物、脂質、タンパク質)のうち、不足が懸念されるのがタンパク質だ。早ければ、2025年~2030年に肉類などに含まれるタンパク質の需要が供給を上回る「タンパク質クライシス(危機)」が起きる可能性が指摘されており、これは世界の人口増加や食生活の変化に伴ってタンパク質の需要が急増するスピードが、畜産に必要な穀物の供給量の増加ペースを上回ることによるものだ。国連の世界人口推計2019年版によると、世界人口は2050年には100億人に迫ると予測される。新興国や開発途上国を中心とする人口増加と所得向上により、肉類の消費の増加が確実視されるのに対し、技術改良などで穀物の生産性を高める努力も続けられているが、不安定な状況は変わらない。
また、持続可能な開発目標(SDGs)で掲げられた2030年までに「飢餓をゼロに」という目標にも暗雲が立ち込める。国連食糧農業機関(FAO)など5つの国際機関が2023年に共同発表した「世界の食料安全保障と栄養の現状」によると、世界の飢餓人口は約7億3300万人で、11人に1人が飢餓状態にある。現在、世界では生産された食料の約3分の1が廃棄されており、この「フードロス」問題が、先進国が「飽食」の状態にあるかたわら、開発途上国では飢餓人口が増えているという「食の不均衡」の構図に結びついている。先進国における食べ残しや賞味期限切れによる廃棄がフードロスの典型だが、開発途上国でも、生産した作物を加工・保管する技術や労働力の不足などの理由でフードロスが発生している。
そして、台風、豪雨、洪水、高温、干ばつといった地球規模の気候変動や、生態系の変化によって、従来の農業や牧畜、漁業の内容が変更を迫られている。気候変動は、熱帯地域や温帯地域で主に作られる小麦・コメ・トウモロコシなどの生産全般に影響を及ぼす。また、沿岸における海藻の群落が消失する「磯焼け」などの生態系の変化や、海水温上昇に伴う漁獲量減少などで、従来の漁業の維持が危機に瀕している地域も多い。
タンパク質危機
タンパク質の需要が畜産に必要な穀物の供給を上回り、近い将来に世界的なタンパク質不足の発生が懸念される
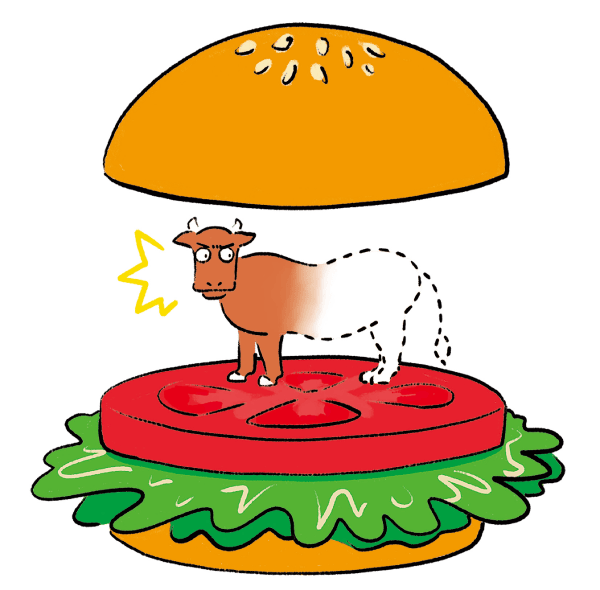
フードロス
世界で生産された食料の約3分の1が捨てられる一方で、7億人以上の飢餓という「食の不均衡」が生じている
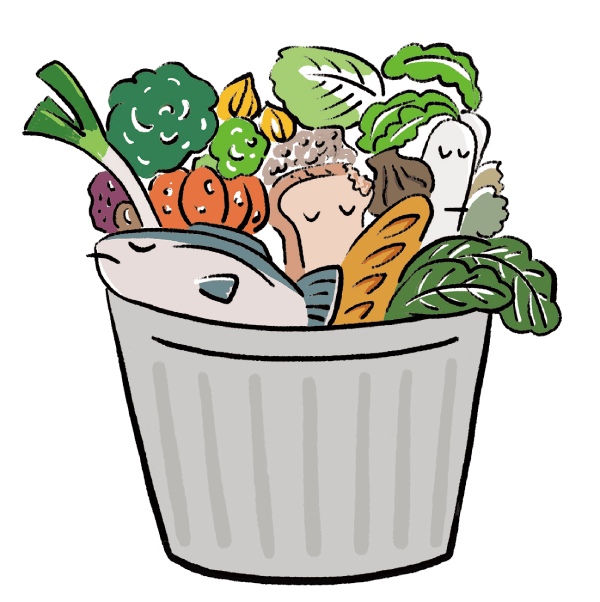
気候変動や生態系の変化
台風・豪雨・洪水・高温・干ばつなどの気候変動で作物の収穫量が減少。生態系の変化は漁業などに影響を及ぼす
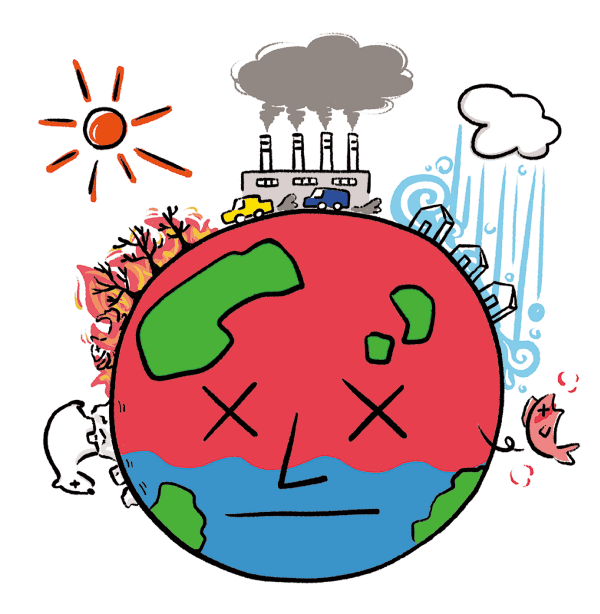
特許取得のフードテックが示す食料生産システムの未来像
これら「食」に関する課題の解消に世界中の企業や研究機関、大学などが取り組む中で、特許を取得した「フードテック」も存在感を増している。例えばタンパク質危機を回避するため、動物の細胞から生み出す培養肉や、大豆など植物性の原料から作られる代替肉(プラントベースフード)の研究が続けられている。環境負荷の低減や厳密な衛生管理が可能といったメリットも多いが、現在はまだ風味やコストに課題を残している。昆虫食や、ゲノム編集による農水産物の高品質化といった試みも注目されるが、こちらは消費者の心理的な抵抗感の払拭が重要になる。代替タンパク質の普及を支援する一例として、食感や栄養素を調節できる3Dフードプリンターも注目されており、食品の残渣や端材、生産余剰農作物を粉末加工する技術などとともに、「フードロス」解消の期待も担う。
今回の特集では、植物由来の無細胞タンパク質合成技術と、沿岸の生態系回復への寄与も期待される海藻の養殖技術を紹介し、持続可能な食料生産システムの将来像を探る。
イラスト:mutsumi
ページTOPへ