ここから本文です。
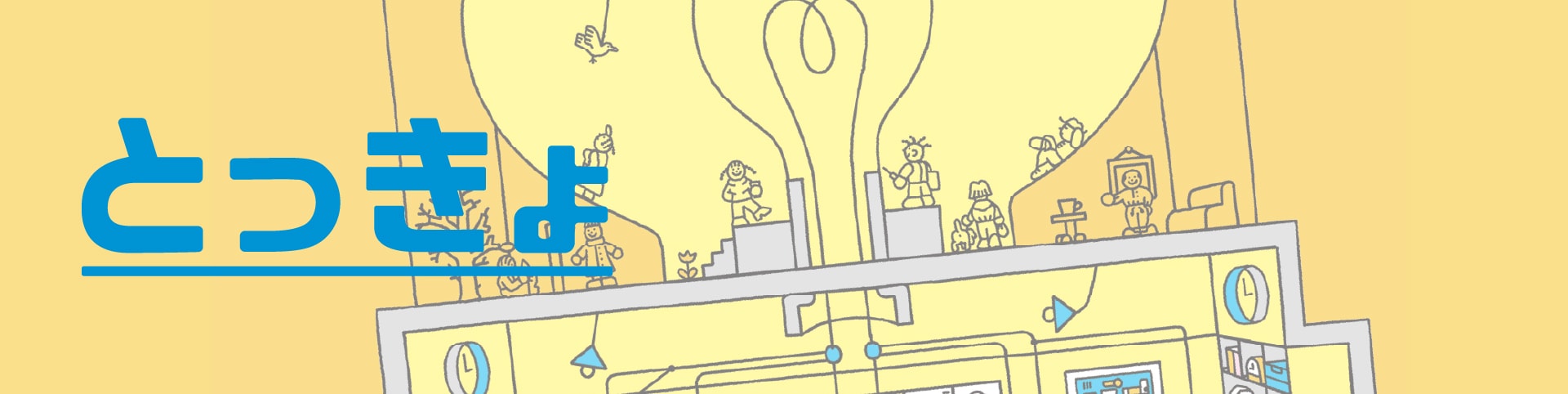
Vol.59
広報誌「とっきょ」2023年12月15日発行号
特集1:未来の知財は「高専」にあり!
全国51校の国立高専の知財の番人を務めつつ、
学生の知財リテラシー教育も支援しています

独立行政法人 国立高等専門学校機構
理事長 谷口 功
国際電気化学会日本代表、熊本大学学長、国立大学協会副会長、日本工学アカデミー副会長、日本化学会筆頭副会長などを歴任。2016年より高専機構理事長に就任。専門は電気化学、生物電気化学。
高専で学ぶ大きな利点は、5年間かけて密度の高い勉強ができることです。基礎から応用まで多様な知識を身に付けつつ、授業の3割から4割を占める実験・実習で経験を重ね、型にはまらない発想を育む高専の学生は、いわばダイヤの原石。かつて高専の社会的な役割は「即戦力エンジニア」のニーズに応えることでしたが、現在はそこに、閉塞した状況を打破するイノベーションの担い手としての期待が加わっています。高専の学生の「とにかくやってみる」という前向きなマインドと、粗削りながら新鮮なアイデアに、企業は大きな関心を寄せています。
そうした背景の下、高専機構はモデルコアカリキュラム(MCC)を策定し、学生が意欲的に学べる環境づくりに努めています。これは全ての学生の到達目標となる「コア」と、一層の高度化を図る指針となる「モデル」を提示したもの。進化を続ける半導体産業を視野に半導体教育を強化するなど、社会の変化に対応する柔軟性とスピード感を重視しており、2024年度の入学生からは、改訂版MCCに準拠したカリキュラムが新たに適用されます。
高専機構は、各国立高専で生まれた研究成果などの知的財産の権利化も担っており、現在までに特許権をはじめ約1,300件を出願し、ライセンス可能な特許情報データベースも公開しています。また、高専の知財の番人を務めるだけでなく、知財教育にも取り組んでいます。高専の学生が知財を学ぶ意義は大きく2つあり、まずは自分たちの権利を守り、他の国と交渉する上で、知財は重要なカードになるという基本的な理解を身に付けること。もう1つは、自分の研究分野の特許などを調べて、自分の研究の水準や現在地を知る指標とすることです。私自身、学生の発表会を見て、これはと思ったものには特許取得の支援をしています。弁理士など専門家の力を借りつつ、学生が特許取得の手続を実際に体験することは、とても貴重な知財教育の機会になりますから。