ここから本文です。
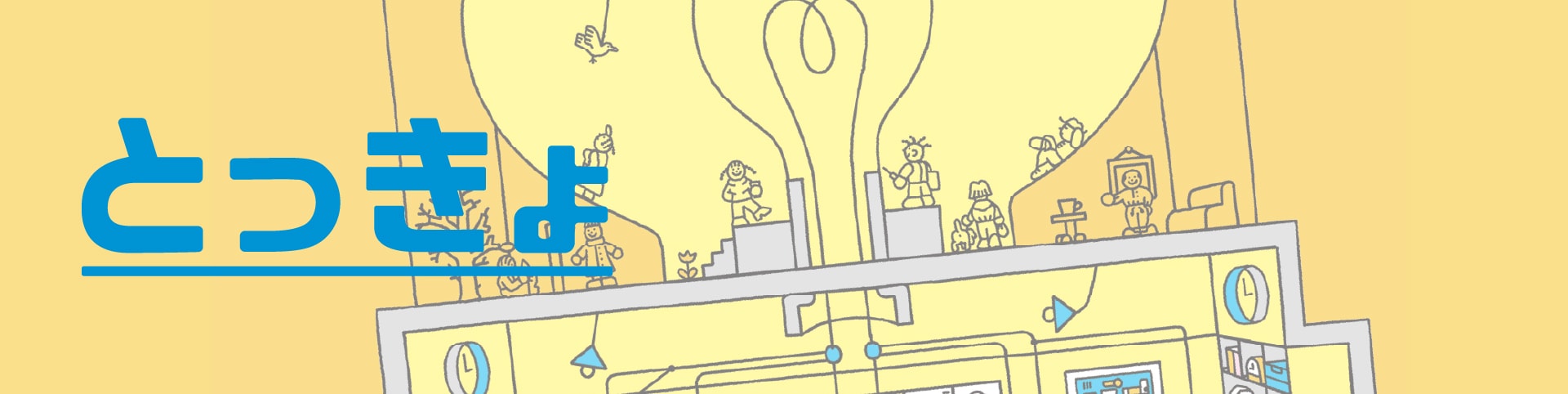
Vol.59
広報誌「とっきょ」2023年12月15日発行号
特集1:香川高等専門学校
「AI×特許」を武器に起業する学生も登場!

各種コンテストの強豪として知られる香川高等専門学校(香川高専)。特筆すべきはこの数年、在学中に起業する学生が次々と登場していることだ。同校で産学官連携プログラムや知財教育を長年主導してきた三﨑教授と、スタートアップで奮闘する教え子たちに話を聞いた。
PROFILE

独立行政法人 国立高等専門学校機構
香川高等専門学校
[所在地] 香川県高松市勅使町355(高松キャンパス)、香川県三豊市詫間町香田551(詫間キャンパス)
[URL] https://www.kagawa-nct.ac.jp(外部サイトへリンク)
[設立] 1962年
[学生数] 本科1,442人、専攻科96人※2023年5月1日現在
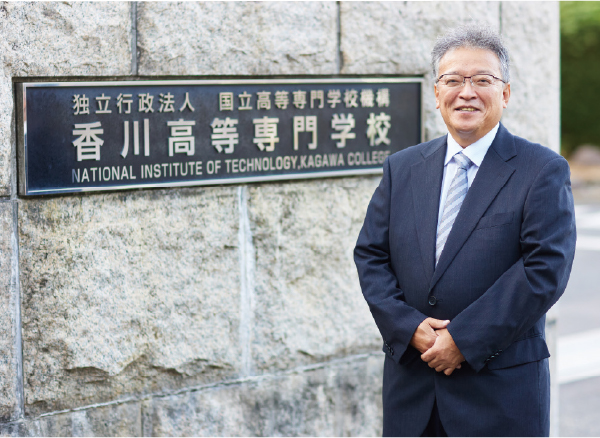
香川高等専門学校電子システム工学科
教授・博士(工学) 三﨑 幸典
「特許庁で女性初の審査長・審判長を務められた須藤阿佐子先生、特許庁出身で山口大学の知財教育体制を構築された佐田洋一郎先生の指導を仰ぎ、INPIT((独)工業所有権情報・研修館)の開発事業他を活用して、香川高専の知財教育や地域企業との共同研究シーズの権利化を推進しました」
知財教育や起業のコアとなる高専ならではの「実用主義」
私が香川高専で知財関連の取組に力を入れ始めたのは、2000年代初頭から。産学官連携プログラムの中で、地域企業との共同研究といった知財の権利化を推進しました。学生への知財教育は、「特許検索の技術を身に付けること」を基本に据えています。J-PlatPat(特許情報プラットフォーム)を使って自分の研究の先行事例を確かめたり、利用できる技術を探したりする以外に、例えば就職を考えている企業の知財に関する動きを調べれば、その企業の戦略が見えてきます。皆が弁理士を目指すわけではありませんし、あくまで技術者や研究者として必要な特許の利用法を学べば良い。高専ならではの実用主義です。
そして知財活用の次フェーズを模索する中、AI研究の第一人者である東京大学の松尾豊教授と出会い、「AIと知財を結び付けた起業」のビジョンを描くことができました。香川高専はDCON(※1)の常連なのですが、さらに入賞した学生たちが、松尾先生の後押しもあって、次々と在学中に会社を設立するに至っています。私はかねて、高専生の進路として地元の優良企業を目指すだけでなく、技術や熱意を生かした起業という選択肢があるべきだと考えてきたので、感慨深いですね。
起業した学生たちが、母校をラボとして活用し、事業で得た利益で母校との共同研究を推進する。後輩たちが、起業した先輩の会社に就職して、また新しいビジネスが芽吹いていく。そんな好循環の実現こそ、未来の高専が生き残る道ではないでしょうか。彼らの挑戦に大いに期待しています。(香川高専・三﨑教授)
※1 全国高等専門学校ディープラーニングコンテスト(DCON)……AIのディープラーニング(深層学習)とものづくりの技術を活用した作品の事業性を競うコンテスト。審査では投資家が具体的な評価額を発表