ここから本文です。
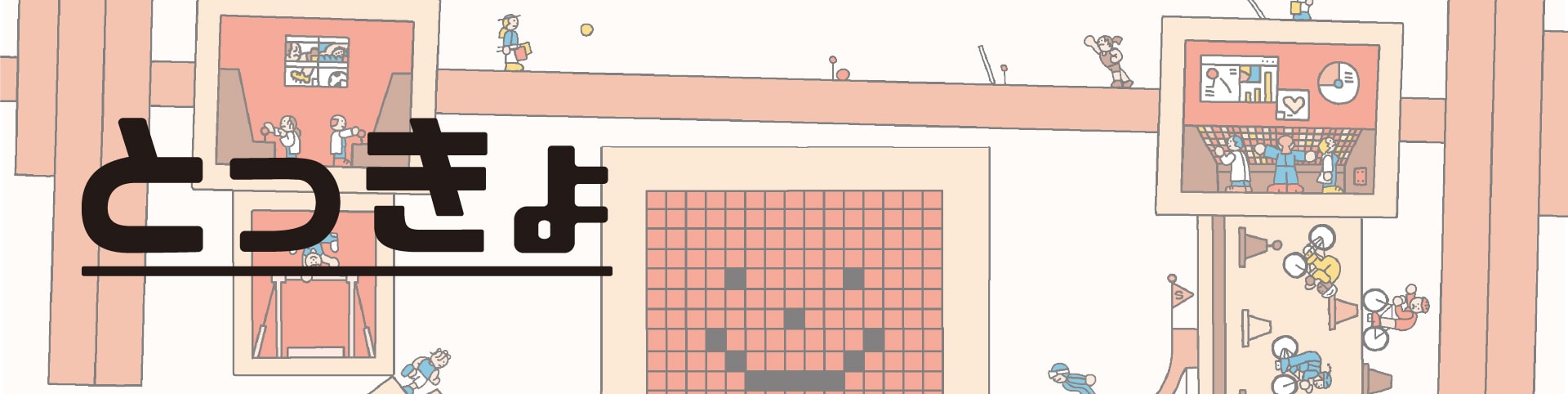
Vol.60
広報誌「とっきょ」2024年3月5日発行号
特集1:知財が変える! スポーツ体験
スポーツテックをけん引する
画像処理・センシング・AI

慶應義塾大学
大学院政策・メディア研究科 教授
仰木 裕嗣
2016年より現職。専門はスポーツ工学・スポーツバイオメカニクス・生体計測・無線計測。水泳選手・コーチの経験や、スポーツ研究支援会社SPINOUT代表としての知見を生かし、産学連携も多数手がける。
私は特許庁の「令和元年度特許出願技術動向調査-スポーツ関連技術-」でアドバイザリーボード座長を務め、特許技術を含めた国内外のスポーツテクノロジーを「みる」「ささえる」「する」の三分野に大別して報告を行いました。それからまだ数年ですが、画像処理とセンシング(センサーによる計測・数値化)、そしてAIの進化には目覚ましいものがあります。一例として、センサーで取得した3DデータとAIを組み合わせて人の動きを数値化し技の判定を支援する富士通の「体操採点支援システム」が、2021年の東京五輪他、世界大会で導入されています。この流れは今後も続き、公平性の担保のため「エビデンスありきのジャッジ」が浸透するとともに、高精度のスマートフォンを持った観客が微細な判定をコンテンツとして体験する「国民総審判時代」を招来するかもしれません。
技術革新が競われる中で、例えばソニーグループ傘下のホークアイイノベーションズ(英)の映像技術は、テニスのチャレンジシステムや、サッカーW杯で使用されているVAR※などですでに市場を席巻しています。ただし、「スポーツ体験」をより広く定義して競技やイベントの運営などを含めると、日本が得意とする「モノやサービスの作り込み」で、新たな存在感を示す道が見えてきます。NECの顔認証システムや、各社が取り組む電子チケット、遠隔応援サービスなどが好例です。また、スポーツ競技の裾野の広さも日本の特性であり、例えば現在、公立中学校の部活動運営を地域の団体や事業者に委ねる「部活の地域移行」の推進が始まっていますが、「地域単位のスポーツ振興」も今後の有望なマーケットになり得るでしょう。
私自身は二十年以上前から、科学的根拠に基づく「エビデンス・ベースド・スポーツ」を提唱し、企業との共同研究も含めてさまざまな特許技術を開発してきましたが、ライフワークとして掲げているのが、センシング技術を活用して全国の「金の卵」を発掘・育成するシステム作りです。網羅的なセンシングの環境整備や、測定データを基に診断やコーチングを行う方法論の探究など課題は多いですが、ぜひ実現させたいと思っています。
※VAR:ビデオ・アシスタント・レフェリー
撮影協力:学校法人誠心学園 浜松開誠館高等学校
写真提供:慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス仰木裕嗣研究室