ここから本文です。
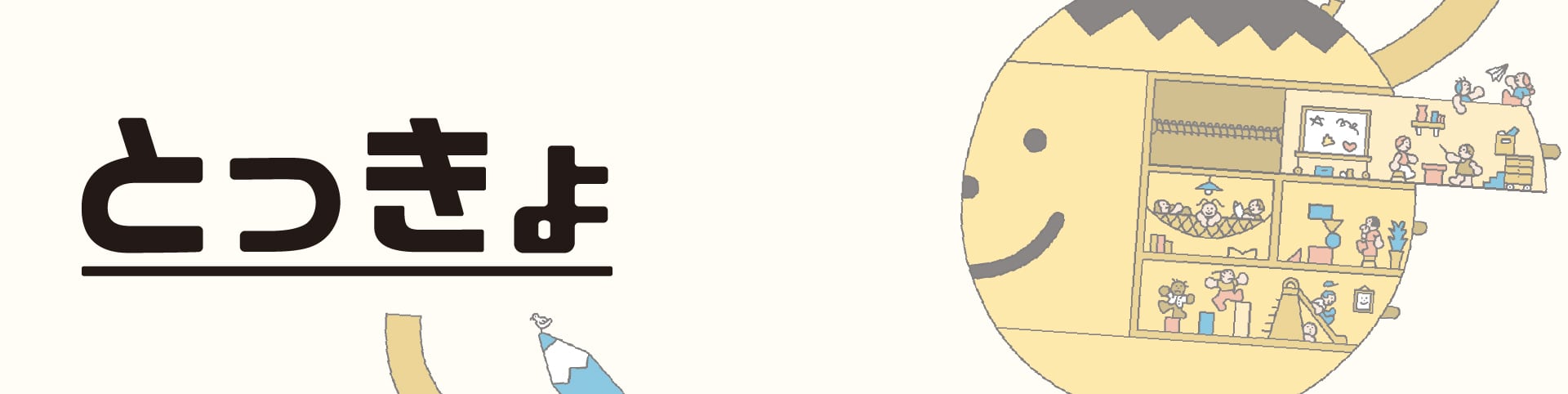
Vol.61
広報誌「とっきょ」2024年7月30日発行号
特集1:未来を創造!発明キッズ
アイデアを「知財」に変えて、社会につなげる物語
未来を創造!発明キッズ

弁理士 知財コンサルタント
金沢工業大学客員教授
栗原 潔
日本IBM、ガートナージャパンでSE、ITアナリストとしての勤務を経て、2005年より弁理士業務と先進IT分野を中心とした知的財産コンサルティング業務を並行して行う。寄稿・講演・ビジネス書翻訳など多数。
生活に根ざした子どもらしいアイデアが特許化された事例が数多くあります
「わが子の発明の特許化」を考えている保護者に向けて、具体的な手続きや費用、また新規性などの留意点について、専門家にガイドしてもらった。
小中学生のお子様でも、自分で思いついた新たな発明(技術的アイデア)を特許化することは可能です。特許を取得した商品を事業化したケースもありますし、そこまでいかなくとも、小中学生時代に特許を取れたということは一生の記念になるでしょう。
特許を取得するためには、特許庁に対して出願手続を行い、審査を受けて特許査定を得る必要があります。発明者が未成年の場合、原則的に保護者の方が法定代理人として出願することが必要ですが、発明者や特許権者はすべてお子様本人になります。特許証にも本人の名前がクレジットされます。実際に出願書類を作って特許庁に出願し、審査段階で特許庁審査官とのやり取りを行うのは、弁理士に委任するのが現実的です。
小中学生は通常は住民税非課税者ですので、特許庁に支払う費用(通常は20万円程度)についてはそのほとんどが免除されます。弁理士費用は、弁理士との個別交渉になりますが、数十万円が目安です。期間は通常1年以上を要しますが、早期審査請求を行って半年以内に審査を完了することも可能です。
特許の対象になる発明は、技術的に壮大なものである必要はありません。空き缶の分別装置、耳を痛めない耳飾りアクセサリ、せんたくばさみの整理器具など、いかにも子どもらしい、生活に根ざしたアイデアがこれまでも数多く特許化されています。特許化のためには、たとえば単に空き缶を簡便に分別したいといった願望だけでは不十分で、どういった仕組みで空き缶を分別するのかが明確になっている必要があります。加えて、アイデアが新しく、自明なものでないこと(新規性・進歩性)が必要です。仮に自分で発想したアイデアでも、既に同じアイデアを別の人が思いついていて世の中に知られていれば、特許化できません。また、自分で出願前にアイデアを公表してしまった場合も原則、新規性はなくなりますが、現在は猶予期間があるので、公表した時から1年以内であれば特許化は可能です。今までに似たようなアイデアが知られていないかの調査、もし似たアイデアがあった場合に改良を加えて改良特許を取るための助言などは、弁理士に相談されると良いでしょう。