ここから本文です。
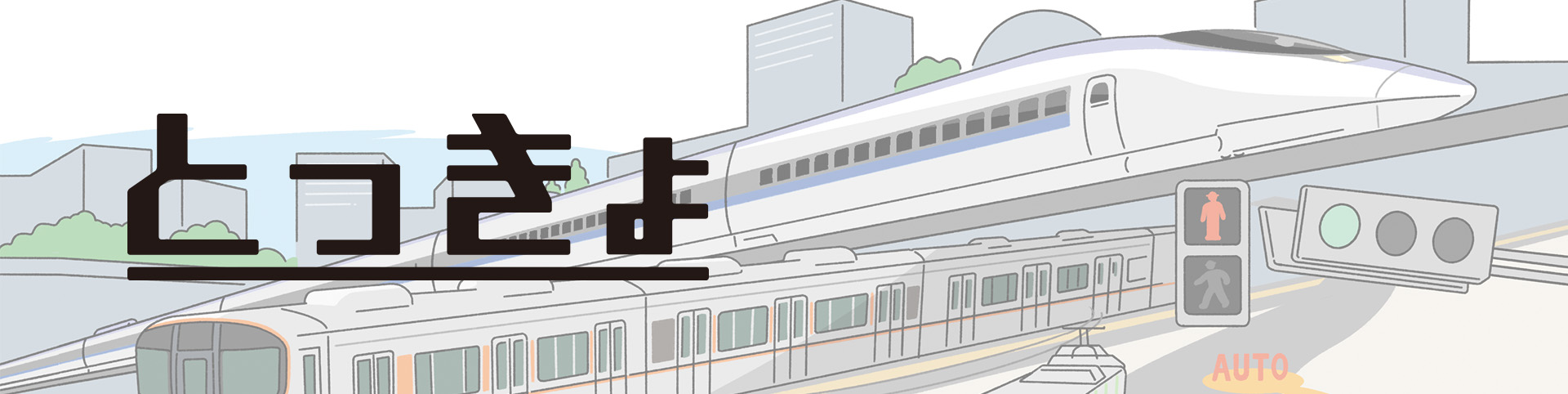
Vol.52
広報誌「とっきょ」2022年3月10日発行号
特集1:西日本旅客鉄道株式会社
“20年後のありたい姿”を実現するために
オープンイノベーションが変える鉄道サービスの未来とは
20年後のありたい姿を技術的に捉えてみよう
自然災害の激甚化や、地方の人口減少、少子高齢化に伴い、鉄道輸送サービスは大きな岐路に立たされています。そこで将来にわたって安全・快適・魅力的かつ持続可能な鉄道輸送サービスの仕組みを作っていくために、20年後のありたい姿を技術的に定め、取り組んでみようじゃないかということで、「JR西日本技術ビジョン」を2018年に策定しました。このビジョンでは、「さらなる安全と安定輸送の追求」「魅力的なエリア創出の一翼を担う鉄道・交通サービスの提供」「持続可能な鉄道・交通システムの構築」という三つの大きな柱を掲げています。
このビジョンを実現していくための方策として重要視しているのが、組織の垣根を越え、広く知識・技術の結集を図るオープンイノベーションです。
鉄道業界はこれまで、重厚長大な仕組みの中で特定のメーカーとウォーターフォール型の仕事をしてきたこともあり、組織文化が閉鎖的で、スピード感に欠けるところもありました。しかし、迅速な技術革新と新たな価値提供を実現するには、このままではいけません。ご存じのように、鉄道は安全第一で、いささかの誤りも許されない、守りが中心の仕事です。実験に実験を重ねて、お客さまに100%のサービスを提供するというのが私たちの事業の性格です。ただ、全てがそれでは、鉄道事業そのものも今日的な「新しい価値」を提供していくことはできません。オープンイノベーションへの取組はある意味、私どもの鉄道事業者としての組織文化も進化させていくという取組でもあるのです。
組織の文化を変えるにはトップのコミットメントが不可欠
とはいえ、オープンイノベーションは社員にとって「未知との遭遇」であり、当初は戸惑いが見られたことも事実です。例えば、部署ごとのデータをAIで横断的に分析して価値が出せるか見極める、というプロセス一つとっても、各部署で守ってきた門外不出のデータを、他部門ましてや外部に提供するなんて、と、現場スタッフからの抵抗は大きかったようです。
こうした組織文化を変えていくには、明確なビジョンと組織トップのコミットメントが不可欠です。そこで、取り組みをさらに加速させるため、2020年に変革プロジェクトを横断的に進めるためのイノベーション本部を設立。また、変化対応力を高め、DXを担うための組織として、デジタルソリューション本部を、社長自らを本部長として立ち上げることとしました。私がブルドーザー役として組織の壁を壊しつつ、取り組みを進めているところです。
実務としては、「リエゾン」というイノベーションの理解者・キーマンを各部署に配置しています。彼らは「社内革命軍」のような存在として、オープンイノベーションを活用した自部門の課題解決などに取り組んでもらっています。社内外の関係者と広く関わりながら新しい考え方を組織に持ち帰ってくる。この繰り返しでイノベーションの輪を広げていくわけです。

小さな成功体験の積み重ねがイノベーションへの自信を育む
成果の一例として、AIを活用した自動改札機のCBMがあります。自動改札機から日々収集される稼働データや故障履歴をAIによって分析、各号機の当面の故障確率を予測し、それに応じたメンテナンスを実施する、というものです。同じ課題は他鉄道事業者さまも抱えておられ、この取組を紹介したところ、実証実験に進むなど、いくつか引き合いも頂いている状況です。このように、当社技術をフックに、外部の方と共創活動を繰り広げる、アウトバウンド型オープンイノベーションに力を注いでいます。
一方、外部の技術を当社施策に取り込むインバウンド型オープンイノベーションの例ですと、電車のドアとホームとの段差・隙間を自動的に解消する機構を開発しています。次代のバリアフリーとして、車いすをご利用の方がご自身で鉄道をご利用いただける環境を整えるためのイノベーションの例で、長野県の小松製作所さまと共に、取り組みを進めてきました。その他、地方交通サービスの実現に向けてBRTシステムの開発をソフトバンクさまと進めているところです。