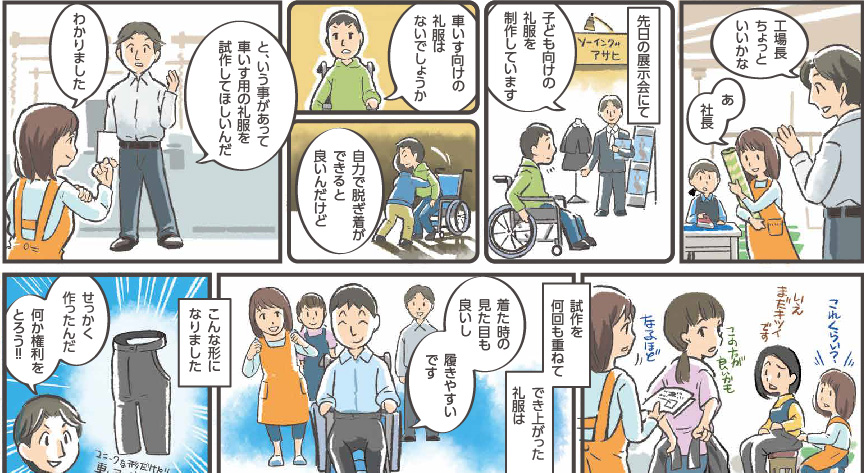ここから本文です。

Vol.38
広報誌「とっきょ」平成30年8・9月号
特集1
知的財産権で守られる
日本の工業デザイン
Honda「スーパーカブ」(本田技研工業)
COLUMN
立体商標登録によるデザイン保護の可能性
商品のデザインを長期間にわたって保護する方法の1つとしてまずは意匠権取得による最長20年の独占状態を築き、立体形状が広く認識され、ブランドが確立した段階で立体商標として登録する方法があります。実際に立体商標登録を成功させた事例を紹介します。
初代モデルを受け継ぐデザインと機能
1958年の誕生から60年。総売り上げ台数1億台を超えるHonda「スーパーカブ」は、今なお最前線で活躍するロングセラーの二輪車です。数度のモデルチェンジを経ながらも、開発当時の基本コンセプトやデザインはほぼそのまま、創業者・本田宗一郎氏の想いを今日まで受け継ぐ唯一の商品です。

「“変えない”と決めているわけではないんです」と、スーパーカブの広報を20年以上担当してきた高山正之さん。「よりよいものになるならば、見た目が変化しても構わない。しかし、機能とデザインを突き詰めていけばいくほど、初代モデルの完成度に改めて気づくのです」。
「女性にも扱いやすい」歴史的大ヒットに
スーパーカブは、宗一郎氏とその右腕であった藤沢武夫氏が「そば屋の出前が片手で乗れるように」として開発。砂利道のような悪路でも安定走行でき、扱いやすく頑丈で、そして女性にも運転しやすいことを目指し、泥はねから衣服を守るシールド、内臓(エンジン部)が露出しないカバーを採用しました。こうして生まれた「スーパーカブC100」は、発売翌年に年間16万台、翌々年には56万台を記録する大ヒット。それを見越した量産体制も奏功し、HONDAは世界的な二輪ブランドとなりました。

半永久的に形状を守る「立体商標」取得への挑戦
出前や新聞配達はもちろん、郵便局員の配達用としても採用されたスーパーカブは、ビジネス用途として揺るぎないシェアを獲得し、海外でも高評価を得ています。
その分、頭を悩ませたのは模倣品の流入です。意匠権は取得していたものの、圧倒的ロングセラーのスーパーカブを意匠権消滅後も守るべく、2010年春、同社の知財担当グループがこの商品の立体商標登録に向けて始動しました。立体商標は半永久的に立体形状を保護できますが、同時に審査の壁も高くなります。「かつて経験したことがないチャレンジでした」と高山さん。
しかし11年2月の出願から2年近く経過した後、拒絶査定となりました。そこで複数の特許庁審判官による「審判手続き」に望みをかけ、広報領域だけで段ボール2箱分の資料をかき集めました。そこには、スーパーカブがいかに認知度の高い商品であるかを示すテレビ番組や書籍などの資料がぎっしり詰まっていました。
14年6月6日、自動車業界としても前例のない、乗り物自体の形状が初めて立体商標登録されました。特筆すべきは、ロゴやエンブレムを取り去った「スーパーカブの見た目」だけで登録が叶ったこと。歴史に裏打ちされた実直な形状こそが、この難しい挑戦を成功に導いたのです。
知財ワード解説 立体商標
立体商標制度は、キャラクターや商品パッケージなどを対象に、立体的な形状の独自性を商標として保護することができる制度です。国内では不二家の「ペコちゃん・ポコちゃん」人形、乳酸菌飲料「ヤクルト」の容器などが登録されています。1996年の改正法によって日本に導入されました。