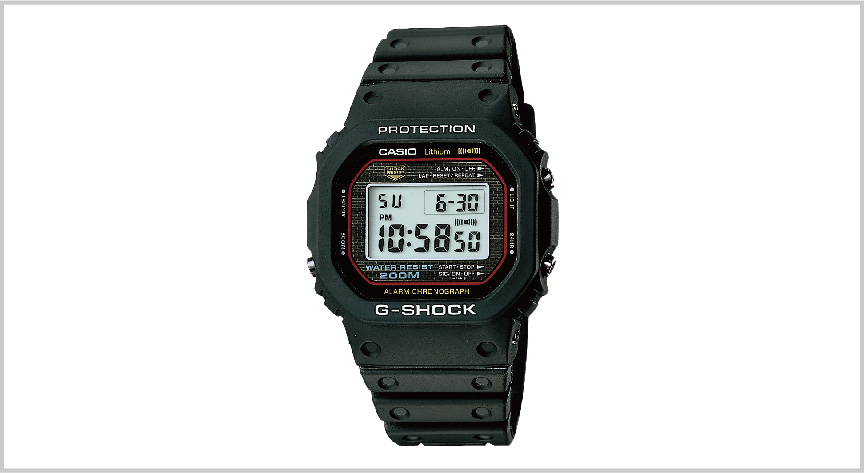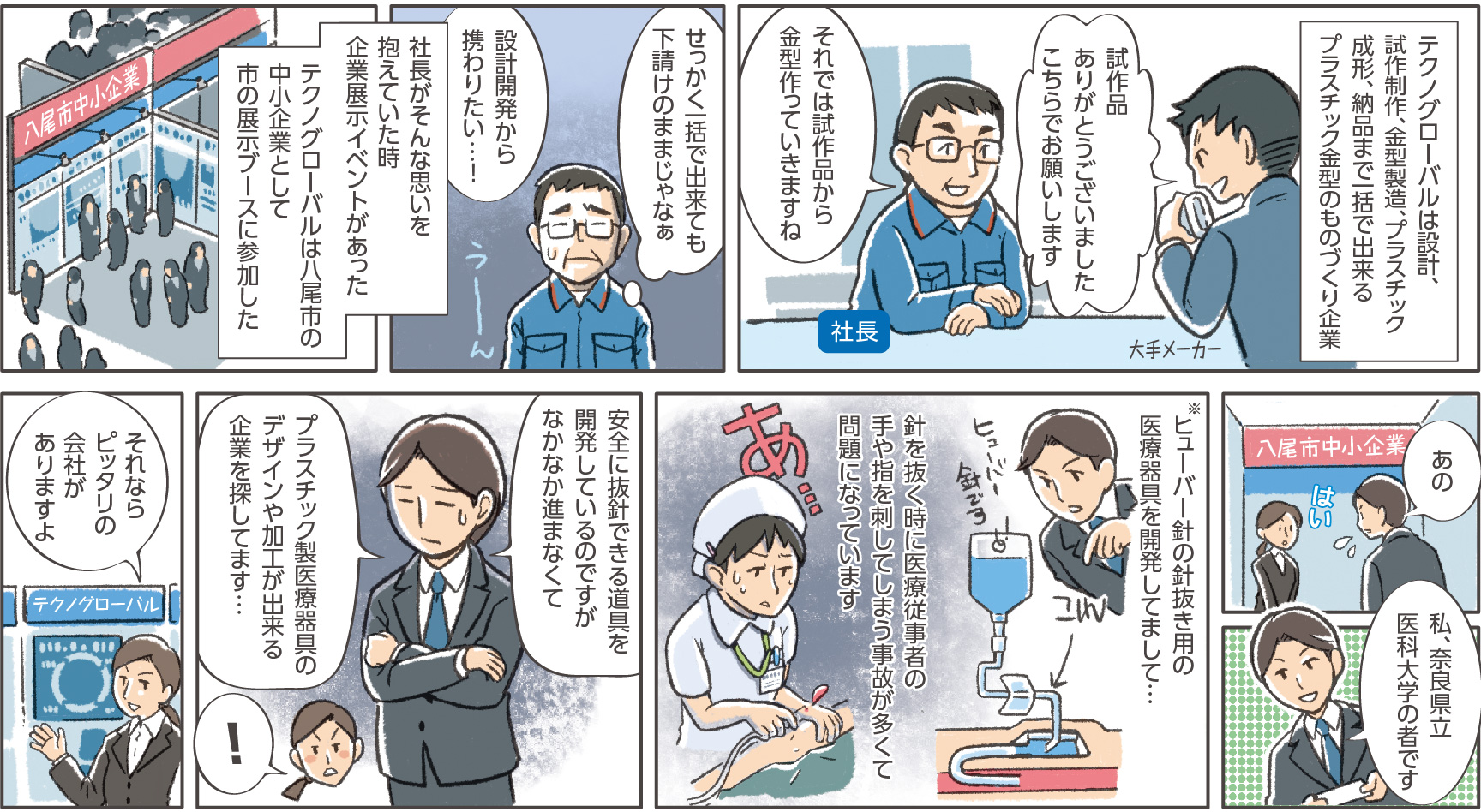ここから本文です。

Vol.41
広報誌「とっきょ」2019年2・3月号
特集1
オープンイノベーション × 知財
カイシン工業(長野県長野市)
大学やメーカーと協業し
農業分野でイノベーションを起こす
ホウレンソウ自動収穫技術で特許出願
1974年の創業以来培った板金加工の技術を武器に、設計から製造・品質管理までの一貫生産を掲げるカイシン工業。現在、同社が特許の権利化をめざすのは、ホウレンソウ自動収穫装置の基幹技術です。これは農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業「軟弱野菜自動収穫ロボット実用化研究開発」の一環で、基礎となったのは信州大学工学部千田研究室の要素研究でした。
傷がつきやすいホウレンソウは、1株1株手作業で収穫されます。人手がいるうえに長時間腰をかがめる過酷な作業のため、人材不足が深刻化しています。
農地が広がる長野県では、農家が抱えるこうした課題が身近にありました。千田研究室では2010年に研究開発を開始し、2015年に企業が参画して実証事業が始まりました。装置の構想は、根切り刃を付けた機械をホウレンソウの畝に沿って前進させ、土の中にあるホウレンソウの根を切りながら収穫するというもの。収穫したホウレンソウは機械に設置されたコンベアによって自動で後方へ運ばれます。
信州大学はかねてから産学連携に熱心で、このケースでも工学部に籍を置くコーディネーターが事業化に向けて奔走。縁があってカイシン工業に声がかかりました。
それまで農業機械の開発経験が一切なかった同社ですが、「不安もありつつ、同時にまだ世の中にない製品を生み出せるチャンスでした。農業分野の経験こそないものの、当社には自動検査機などのオートメーションの実績があり、新しい機械への挑戦は非常に魅力的でした」と、開発部の大峡慎二部長は話します。

同機の設計開発を担当する開発部開発第三課設計係の天白久司さんは、「機能を追求すると精密機器化してしまいがちですが、農機には耐久性が求められます。毎日の使用に耐える頑丈さを持たせるために研究を繰り返しました」と振り返ります。参画から2カ月で1号機、1年後には市販の農業機械を参考にした2号機が完成。コントローラーを簡素化し、前後に揺れて不安定だった胴体は畝をまたぐ形に変更。また、ホウレンソウの収穫の仕方も大きく改良しました。収穫時に傷も土も付かないよう、ホウレンソウが植えられた形のまま収穫できるように改良したのです。
「農家の方から『ホウレンソウに土が付かないようにしてほしい』と言われたのです。ホウレンソウは、傷や茎折れを防ぐのはもちろん、汚れないよう丁寧に収穫され、わずかな土は1つずつ拭っているそうです。そうした現場の声を優先して開発しました」(天白さん)。

農機メーカーとの共同開発でついに販売へ
しかし、続く3号機の試作で、エンジンや油圧機など、農機メーカーのノウハウが必要な箇所が見つかりました。そこで、千田研究室で他の実証研究をしていた片倉機器工業(長野県松本市)に協力を要請したのです。老舗の農業機械メーカー・片倉機器工業は農機開発のプロフェッショナルで、農業機械に必要な専門的技術を有しています。すぐに共同開発契約を結び、ノウハウを共有して2017年に3号機を完成させました。

「自社でゼロから開発しようと思ったら何年もかかってしまいます。それぞれの専門性や強みを活かせる共同開発は、本事業の起爆剤となりました」(大峡部長)。
現在は、約1年後の試験的な販売を視野にさらなる改良を重ねています。「本事業では、複数の企業が強みを持ち寄り、同時に研究開発を進めています。最終目的は同じでも、描いている形が少し違えばトラブルにつながります。役割分担を明確にし、ベクトルを合わせることで、より大きなイノベーションが生まれると思います」と大峡部長は話します。

天白さんは「メンテナンスがしやすいよう複雑な形状を避けているので、技術者が見ればすぐに作れてしまうかもしれません」と話します。しかし、そこに至るまでの開発ノウハウには自負があり、経営的にも発売前に特許による権利化が必要と判断しました。今後、販売や保守対応の体制を整えるとともに、長く使ってもらえる親しみやすい名称をつけて商標で保護することも考えています。「収穫に苦労している野菜は多いはず。農家の方の意見を聞きながら、新たな農機のブランドを作っていくのが理想ですね」(大峡部長)。