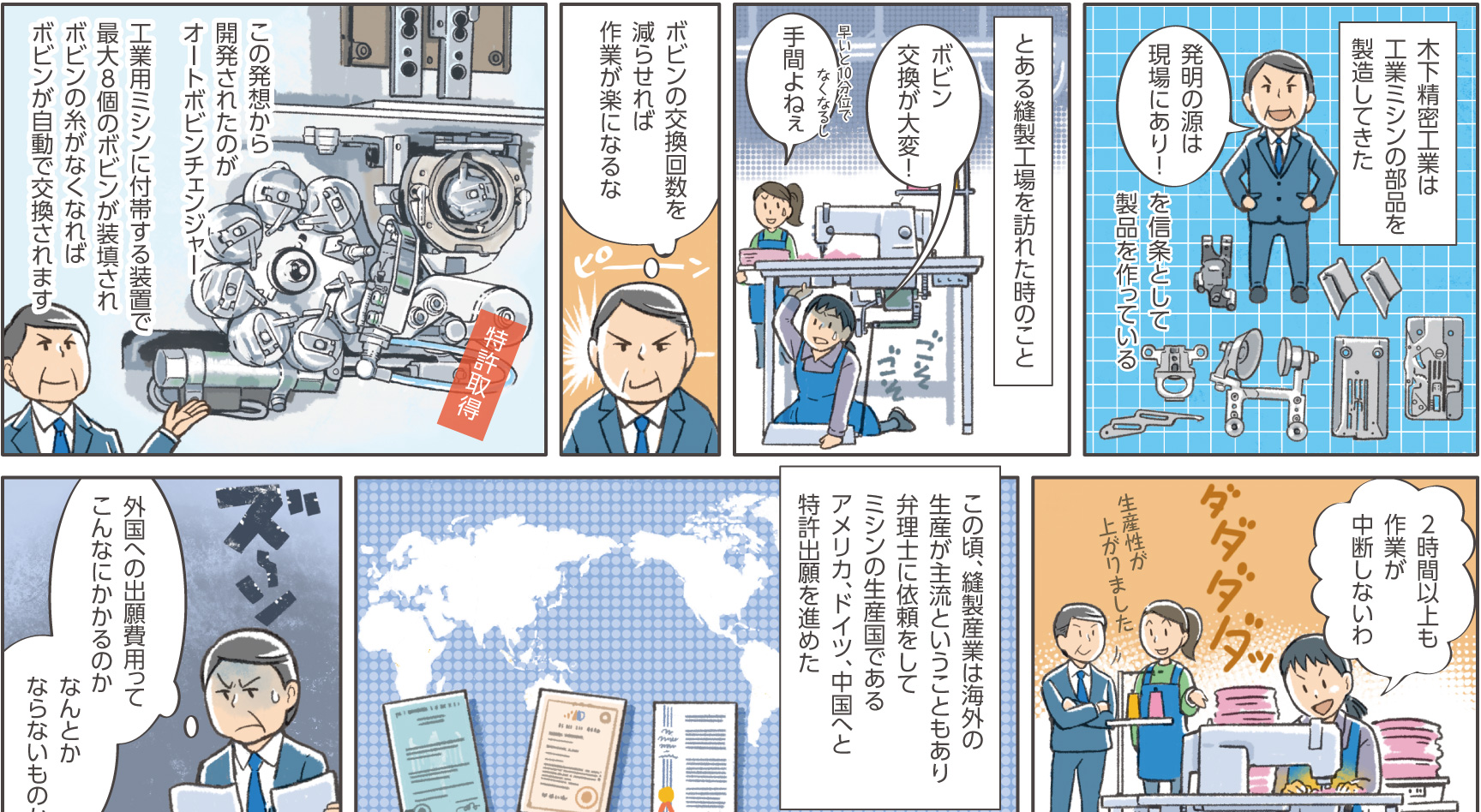ここから本文です。

Vol.42
広報誌「とっきょ」2019年4・5月号
特集1
世界で勝負する中小企業の知財戦略
特許協力条約(PCT)に基づく特許の国際出願制度
ローツェ(広島県福山市)
半導体メーカーの海外進出とともに海外拠点を展開して知財を獲得
半導体メーカーを支える縁の下の力持ち
「世の中にないものをつくる」という信念のもと、半導体の製造工場で使用されるウエハ搬送装置などの開発・製造を行うローツェ。ごみの発生や汚染がないこと、故障しにくいことなど、約600の行程に細分化された半導体製造工程で求められる品質を高い精度でクリアし、国内外の半導体メーカー、半導体製造装置メーカーから高く評価されています。また、同社が開発したダブルアーム仕様の搬送ロボットは従来の3倍の搬送能力を有し、ユーザーの歩留まり(製造ラインで生産される製品から不良製品を引いた割合)向上に貢献しています。
こうした技術は、基本的に社内で特許出願の手続きを行います。発明者の「出願申請書」をもとに、知財担当者が先行技術調査を行い、項目ごとに評価。この「特許評価シート」を役員、技術部長などが参加する出願検討会で提示し、出願可否を決定します。
そして1年以内に外国出願も検討。以前は国内出願のみの技術が多かったものの、近年は積極的に海外への出願を進めています。
「最初の外国出願は1993年で、ダブルアーム仕様の搬送ロボットの特許を韓国で取得。次に、ウエハを半導体製造装置に出し入れするロードポートの特許をアメリカ・韓国・台湾・ドイツに出願しました」と話すのは、社長室で知的財産担当を務める掛谷信樹さん。その背景には、国内の半導体メーカーが次々に製造拠点を海外に移したことがあるといいます。


「半導体メーカーが拠点を移すなら、私たちも現地で生産・保守対応するのが当然。また最近では、国外の半導体メーカーの台頭とともにさらに海外展開に注力しています」と掛谷さん。現在はアメリカ、韓国、台湾、中国、欧州など、顧客の拠点がある地域を中心に、主にPCT国際出願による特許出願を行っています。「開発当初は、その技術の将来性が判断しにくい。PCT国際出願制度を使えば、国内出願から最大30カ月まで検討できるのが助かります」(掛谷さん)。海外での保有特許は90件に上りますが、「中小企業海外出願支援補助金」を2回利用し、出願コストを抑えています。

海外に子会社や製造拠点を次々と設立
1996年に台湾、シンガポール、アメリカに子会社を、生産拠点をベトナムに設立。翌年に韓国、2008年には中国に子会社を設けました。当時、こうした業種でベトナムに生産拠点を置いたのは同社が初めて。その理由には、アルミ二ウムの調達コストや電力コストの安さ、勤勉な国民性が挙げられます。現在は日本で設計・開発を行っていますが、今後ベトナムでの設計・開発が可能になれば、現地での独自出願も必要になると考えています。

今後は、半導体メーカーが保有技術を活用して参入しやすい創薬・ライフサイエンス分野にも力を入れていくそう。掛谷さんは「特に海外メーカーは、新規取引の際に特許件数で信頼性を判断することが多い。海外での事業拡大のためにも、知財を取得・管理していく重要性を感じています」と語りました。