ここから本文です。

Vol.43
広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号
AIに関する特許庁の取組
– 今回追加事例を作成した背景を教えてください。

審査第一部調査課 審査基準室 室長補佐 齋藤正貴
齋藤:私たち審査基準室は、「特許・実用新案審査基準」を整備しています。これはどんな発明が特許を取得できるか、その考え方をまとめたものです。さらに、この考え方を審査官と出願する方の双方に分かりやすく伝えるために事例集を作成・公表しています。
当室は過去にもIoTやAIの関連発明に関し、審査のポイントを分かりやすく伝えるべく合計23の事例を作成・公表してきました。その後、昨年春頃からAI関連発明に関し特許取得のための考え方について多くの質問を受けるようになり、こうした関心の高まりを受け今年1月、新たにAI関連発明の10の事例を追加公表しました。
– 追加事例の特長を教えてください。
審査官が発明のどこに着目して特許性を判断するのか、出願する側はどの点に注意して書類を作成すればよいのかを各事例に記載しました。特許性が肯定される事例だけでなく、否定される事例も紹介することで、10の事例全体で審査のポイントを分かりやすく示しています。また、今後のAIの発展を見越して化学、機械、電気、農業やその他多くの分野を網羅し、これまでAIとは無関係だった企業にも関心を持ってもらえる事例にしています。
– AI関連発明の基準や事例について、今後の特許庁の動きを教えてください。
今回の追加事例も含め、まとまったAI関連発明の事例の公表は世界初のものです。今後は、この事例を基に海外の特許庁と議論し、判断基準の国際調和を目指したいと考えています。それによって、日本企業が海外でAI関連発明の特許を取得する際にも特許取得の予見性、可能性が高まるものと期待しています。
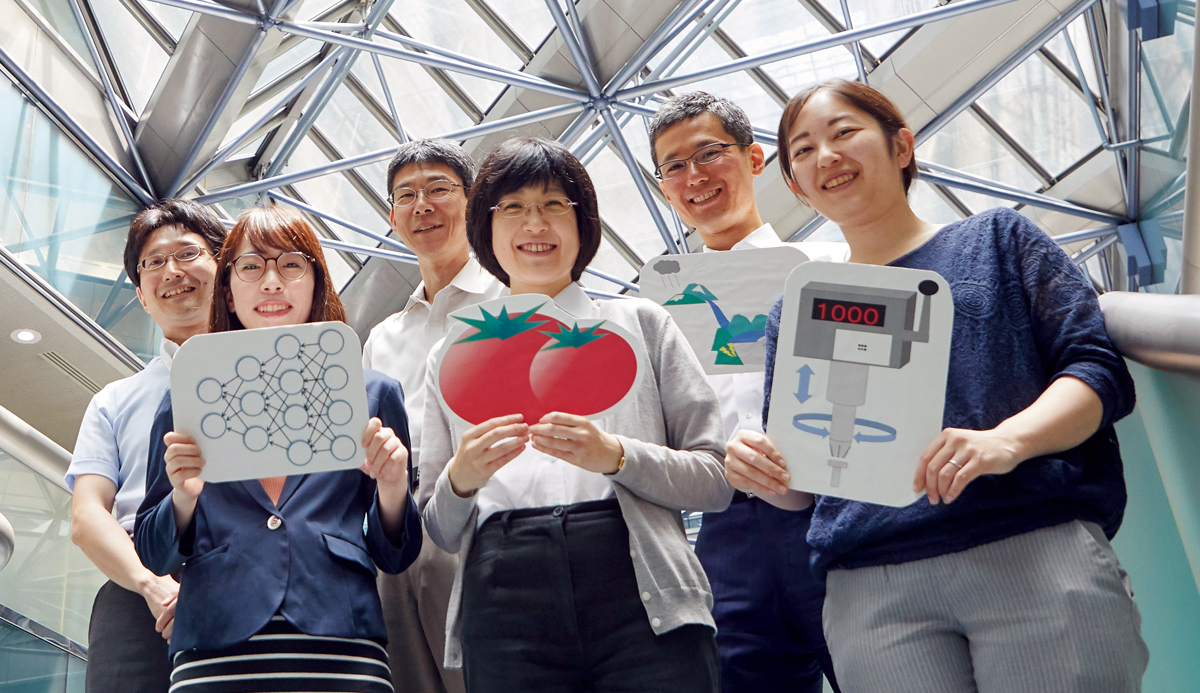
AI関連発明の審査事例の作成にあたり、農業、発電、工業など多分野を網羅した内容であることをイメージしたイラストを手に。
少子高齢化が進む日本で、AI技術は予想される労働力不足を補うために必要なものです。AIは、分野を問わず、人間がこれまでに得たデータを基に判断を行い、人間の「補助」として機能してくれるもの。今後AI関連発明がますます増え、それらが適切に特許として保護されビジネスに使われることで産業が活性化されることを期待します。
詳細はこちらからご覧ください
Vol.43 Contents
広報誌「とっきょ」2019年10月7日発行号 コンテンツ紹介
-

- IPランドスケープで俯瞰するAI
- 「プロダクト・サービスの今と将来市場」「特許出願データから各企業のAI力を予測」「AI技術の今後に関する期待と懸念」など「IPランドスケープ」の観点でお話しします。
2019年9月25日
記事を読む -
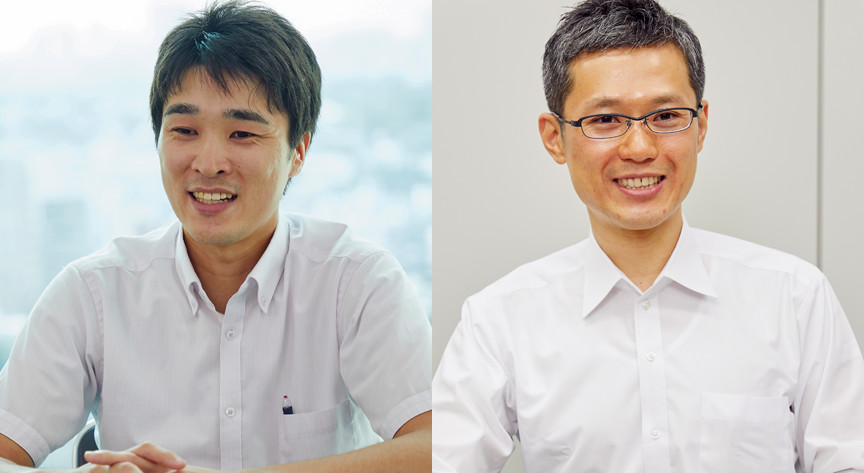
-

-

- あなたの悩み、解決のお手伝いをします
INPIT 知財総合支援窓口へようこそ!
CASE6 株式会社幸呼来Japan - INPITの知財総合支援窓口が対応した支援事例をマンガで紹介。第6回は伝統技術「裂き織」に光をあてる知財の活用事例。
2019年9月18日
記事を読む - あなたの悩み、解決のお手伝いをします
-

-

-

- あのとき、あの知財 大ヒットの裏側を探る!
いつでも新鮮®しぼりたて生しょうゆ(キッコーマン株式会社) - 業界の概念を変えた“生しょうゆ”と100年以上変わらぬ「萬」マーク
2019年9月18日
記事を読む - あのとき、あの知財 大ヒットの裏側を探る!